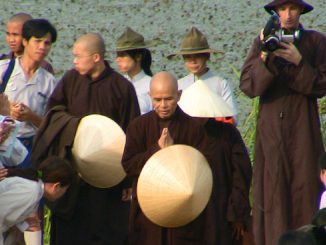ベトナムでの外国人の暮らし:局部的なエスノグラフィー研究
背景 はるか昔から、移民と文化交流はベトナムの文明・社会の求心力となってきた。この地域では、三方向での絶え間ない文化交流が見られる。つまり、中国北部の諸王朝出身の北方移民とデルタの地元住民との交流、デルタ西・北西部の山岳部族とデルタの交流、デルタとその南の地域、チャンパとの交流である。さらに、ベトナムは、ベトナムの経済、文化の発展に寄与した西洋の外国人も受け入れてきた。例えば、アレクサンドル・ロード神父(Father Alexander Rhodes)が、ポルトガル由来のラテン文字を使い、聖書をベトナム人向けに翻訳した話は有名である。さらに、ベトナムでは、20世紀にラテン文字一式が導入され、従来の漢字とノム字(Nom script/漢字とベトナム語の発音を組み合わせ応用した文字)が廃止された。皮肉にも、植民地主義に対する国家の存続と、アイデンティティ強化の名の下で、外国語は基礎教育の普遍化に非常に重要な役割を果たした。 ドイモイ(Doi Moi/刷新)は、安全保障化された(securitized)戦争中心の経済・社会の時代を終らせ、社会活動と経済活動による国際交流ができる社会という新時代の幕開けをもたらした。だが、外国人に接し、彼らについて学び、受け入れるプロセスは一様ではなく、その開始には時間がかかった。例えば、あるインド系の外国人が1993年(ドイモイ開始から6年後)にディエン・ビエン・フー(Dien Bien Phu)を訪れたことを報告しており、同地域で、それまでに浅黒い肌をしたインド人を見た人が一人もいなかったことに驚いたという。 実際、戦時中は、非友好国出身の外国人がベトナムに住む事は、ほとんど禁止されていた。また、外国人は客人とされるため、ベトナム流の歓待を示さねばならず、彼らはベトナムが提供しうる最高のサービスと物を望んでいるだろうと考えられていた。このため、外国人は特別な居住区に住まねばならず、特別な注意を向けられ、手に入る最高のサービスと物が提供された。だが、スーパーマーケットが無かった頃、ハノイの外国人は、自国に特有の日用品が欲しくなると、(ライセンスが必要な)特別な輸入品を買わねばならなかった。つまり、外国人にとって、ベトナムは住み心地の良い滞在国ではなかった。 だが、それから30年後の2010年代には、経済における外国人の役割の重要性が高まり、外国人を受け入れるのに必要な調整が行われた。現在、国境付近の辺境の地方の特定の少数民族地域を除き、ベトナムにいる外国人は、どこでも住みたい場所に住んでいる。それに、外国人の専門知識が大いに必要な新興経済国、ベトナムでは、外国人に対する態度や、外国人向けの物やサービス、住環境も改善されている。 この40年間、ベトナム社会主義共和国では、経済成長、あるいは、ビジネス関係、友人関係、国際結婚などの人的交流を理由とした大量の移民や、外国人に好意的な地域の形成が見られる。また、外国人の存在と、彼らのニーズを受けて、都市や地方の景観、社会情勢にも変化が生じた。 そもそも、今回の特別号の構想は、ベトナムの環境下で、外国人がどのように暮らしているかを理解する必要性から生じた。ここで、さらに重要な問いは、ベトナムはどのような環境で外国人を受け入れてきたかということだ。ちなみに、ここで言う「環境」とは、(医療、教育、娯楽、銀行取引や消費などのサービスを含む)生活環境や住空間のあり方、国内での活動のしやすさなど全般を指す。そして、これらの有形現象の根底には、ベトナムの国家と社会の外国人に対する一般的な態度がある。 概念入門にあらず この一連の記事に対するもっともな批判として、概念的用語の明確な定義と、理論的裏付けの欠如があると思われる。だが、これは今回の特別号の目的とするところではない。むしろ、ここでの目的は、概念研究や、フォローアップの理論研究の確たる基盤となりうる民俗学・人類学の文献を提供する事にある。そのため、ここで概念や理論を論じるつもりはない。ただし、Phan Thi Hong Xuanらの記事(1)を見ると、アカルチュレーション(Acculturation/文化変容)と、合理的選択(Rational Choice)の手法が彼らの研究を特徴付けているのが分かる。そこで、読者には、この特別号の限られた紙面の制約の外で、これらの概念を十分に検討してもらいたい。 副次的な問い とはいえ、今回の特別号には、きっかけとなる問いがいくつかあった。中でも、次の問いに対しては多面的な答えを求めた。それらは、ベトナムにおける外国人の暮らしはどのようなものか?外国人の暮らしがベトナム社会にどのような影響を与えたか?という問いだ。このプロジェクトに関心を寄せ、研究に携わる研究者の会議では、都市化と、ベトナムへの移住が注目するべき2つの重要な展開として特定された。以下に、寄稿者の研究に対する編集者の考察を述べる。 国内の外国人という存在の社会的影響 現代ベトナムにおける外国人流入の社会的影響は多岐にわたる。まず、Nhutの論文は、外国人をベトナムの生活様式に確実に適合させるために、一連の政策の中に外国人を包摂しようとする国家管理の存在を明らかにした。これには(国旗掲揚式などの活動により)、ベトナムに共通する価値観への理解を深めたり、外国人を招き、地域での集会を開放するなどの例がある。だが、外国人との交流が地域社会に与えうる多様な影響に対して強い懸念も見られる。このような懸念には、国家が国の安全保障に悪影響を及ぼすと見なす外国人の思想や行動、そして、現地の様式に同化されるべき外国人の生活様式に対するものが含まれる。だが、これは、社会の様々な成員を連携させるために社会主義社会が用いる動員手法の一つで、理解と関与を通じて政権支持を促そうとするものである。また、結束した社会には社会的対立が少ないという考え方は、統一や自治国家を重視する社会、すなわち、社会によって権力が脅かされる事のない社会の特徴であり、(1980年代までの)韓国や、(現在も)シンガポールなどの国に見られる特徴である。 さらに、HungとThanhの記事では、外国人には、高い生活水準を求めるニーズがあり、金銭的ゆとりもあることが指摘されている。また、この記事によると、ベトナム政府は、以前の都市の様子とは雰囲気も見た目も大きく異なる新都市計画を、早くも1980年代後半には立てていたようだ。 実際、フーミーフン居住区(the Phu My Hung township)は前代未聞の計画で、20年後の現在でも、規模でこれに匹敵する計画はどこにもない。また、フーミーフンの街並みは、外国人の都市環境に対する好みに応じる必要性を踏まえて計画されている。具体的には、清潔で広い道路や、秩序ある人々の振る舞い、ゴミの撤去から学校、市場の経営に至るまで、衛生的で整理された生活様式である。だが、同じ記事のタオディエン(Thao Dien)の事例分析からは、フーミーフンに見られるような秩序には満たないレベルでも、外国人がある程度許容する様子が伺える。 概念入門にあらず この一連の記事に対するもっともな批判として、概念的用語の明確な定義と、理論的裏付けの欠如があると思われる。だが、これは今回の特別号の目的とするところではない。むしろ、ここでの目的は、概念研究や、フォローアップの理論研究の確たる基盤となりうる民俗学・人類学の文献を提供する事にある。そのため、ここで概念や理論を論じるつもりはない。ただし、Phan Thi Hong Xuanらの記事(1)を見ると、アカルチュレーション(Acculturation/文化変容)と、合理的選択(Rational […]