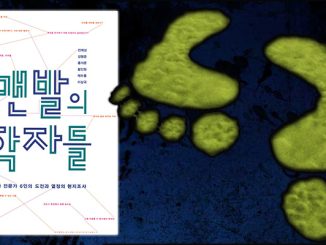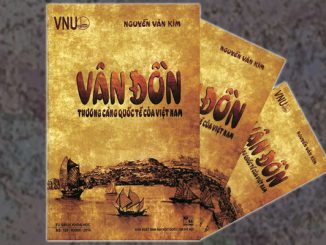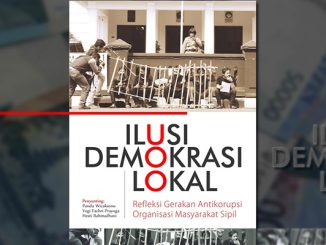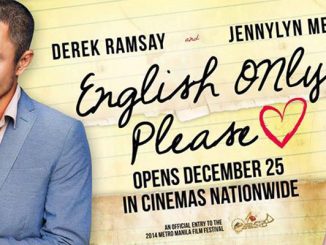タイにおける不平等と政治
よく知られているように、『アメリカの民主主義』の記述において、アレクシス・ド・トクヴィルは「境遇の平等」をアメリカの民主主義の基本でだと言明している。これはタイには当てはまらない。というのも、境遇の不平等こそが、タイの民主主義を規定しているからだ。したがって、トクヴィルの言葉を次のように言い変える事ができる。タイの不平等は社会の動きに甚大な影響を与える。それは国家イデオロギーに一定の方向を与え、法律にある傾向を付与し、為政者に従うべき原則を与え、被治者に特有の習性をもたらす。この不平等の影響は政治や法律を超え、はるか広範に及ぶ。それは世論を創り、感情を生み、慣習を導き、それと無関係なものすべてに修正を加える。タイの不平等は根源的事実であり、全てはそこから生じる。 貧困、所得と不平等 タイにおける経済的、政治的な不平等は、お互いを強化し合う関係にある。それは高度経済成長の利益をエリート達が占有する過程で生まれた。エリートの特権の保護が、排他的で権威主義的なエリート支配の政治構造を生み出しているのだ。1950年代以降の高度経済成長期の大半を通じた独裁的政権の支配が、資本主義の発展を促し、資本家や中産階級を生んだ一方で、政治的権利は制限されてきた。成長は貧困を削減したものの、不平等は依然として高水準にとどまっている。つまり、成長は多くの者達に利潤をもたらしはしたが、資本家階級とその仲間たちがその利益を占有していたのである。 成長が不平等の減少をもたらさなかったのは、所得の増加が富裕層に集中していたためである。0.45から0.53というジニ係数は、1980年代以来、高い水準にとどまったままで、その他の富の測定値も同じような結果である。2007年のデータによって明らかとなったのは、トップ10%の家族が富の51%以上を保有する一方で、下の50%は8.5%の富を保有するにすぎないという事だ。土地や家屋、その他の財産については、人口のわずか10%が私有地の約90%を所有している。別のデータは労働から資本への所得再配分を示すもので、労働の生産性向上に伴い、利益が増加した事で、大いに資本が蓄えられている。2011年の後期まで、低迷した実質賃金がこのパターンの一部であった。. 不平等をどう説明するか この搾取と不平等のパターンは、長い間存在してきたものである。事実、研究者たちは上述のデータと似たようなデータを、数十年の間、引用してきたのだ。1960年代にBellは、貧しい東北地域から巨額の黒字が移転され、この地域を「低開発地域化」させた事を明らかとしたが、これは生産者たちが低賃金と不十分な農業利益で搾取されていたためであった。 30年後にはTeeranaが、貧困削減が所得格差を縮めないという結論を出し、タイにおける不平等が、他のアジア諸国よりも高い事を示した。 なぜ不平等は存続するのか。最良の答えは、国の政策と資本の構造的な力にある。 国家と政策 政策の研究は長年に渡る農村部と都市部の分断を指摘している。国家主導の産業化の結果、より多くの労働者階級が生じたが、資本集約度が高かったため、産業部門は農村部から都市部に出稼ぎに来た移住者たちを吸収できなかった。結果、巨大なインフォーマルセクターの中で、労働者達が国家の限定的な福祉制度の外に取り残される事となった。国家の再配分の対象が小規模なフォーマルセクターに限定されたことで、ますます不平等になった。 同様に、国家の教育投資も都市部に集中してきた。経済が急成長した時代、国家の教育のための支出は、長い間、低いままだった。1960年代の農民や労働者達が人口の85%を占めていた頃に、大学生の15.5%のみが、これらの階層出身であった。1980年代の半ばには、この割合が低下し、わずかに8.8%となった。つまり、下層階級は低賃金や単純労働を脱するための出世街道から除外されていたわけである。 課税政策も貧困層に対して差別的であった。製造業の保護によって農業は冷遇され、また何十年ものあいだ、米の逆進税が地方から都市に富を移転させてきた。1990年代まで、一連の逆進税を通じて富裕層は課税制度から利益を得てきた。2012年の国家の財政政策および支出は、金持ち贔屓にとどまっていた。これらの諸政策の影響によって、貧者から富者への再配分が行われてきたのである。 これらの諸計画を補完してきたのが、政府や企業によって継続されてきた低賃金・高収益政策で、これが富を資本家へと移転してきたのである。 階級と権力 この低賃金・高収益政策の継続に必要となる政治権力は、国家と企業との一連の戦略であり、法律や政策、イデオロギー、そして抑圧にまつわるものである。高度経済成長期の大半を通じ、サバルタン(従属的社会集団)を巡る政治は限定的で、しばしば厳しく抑制されてきた。このような階級に根差した戦略は、選挙政治を制限することで権威主義的体制を維持せんとするものであった。 恩顧主義、あるいは「金権政治」は、カネという特定の利害にもとづく政治的な支持を集める事によって、不平等に対する政策上の注目をそらすものになった。少なくとも2001年まではこれが支配的な傾向だった。選挙が行われた時に、あまりに多くの政党が関与する事となったため、連立政権は常に弱く短命であったし、関与した政党が地元の補助金以上の政策を展開させることは一度も無かった。この政策が多数派を締め出し、代議制を無力な状態に保ち、軍部と王室の支配を可能としてきたのである。その結果、不平等は政界のエリートたちから顧みられず、排除された集団は再配分問題に対する計画的な配慮よりも、むしろ排他主義的な政治利益を受け入れざるを得なかったのである。少なくとも、タクシン・シナワットが2001年に当選するまではそうであった。 不平等への対応 不平等とそれを維持する構造に対して異議が唱えられている。ごく最近では、2009年と2010年に行われ、長期に及んだ赤シャツ派の抗議が、そのような異議の一つであった。2006年のクーデターを拒絶する大勢のなかで、民主化に関する論争に不平等が関連付けられるようになった。この関連付けは、一連の政治・経済的危機、すなわち1991年の軍事クーデターに始まり、続く1992年5月の市民蜂起、そして1997年に長く続いた急成長が終焉した結果として生じたものである。1997年の憲法は、その結果として誕生したものであり、これが政治支配を変える事となった。 1997年憲法の下で選出された唯一の政権は、2001年と2005年のタクシン政権であった。1998年に結成されたタクシンのタイ愛国党(TRT)が、選挙で人気を博したのは、その政策が貧困層のための改善を公約するものであったためである。農民の借金返済の猶予や、地域レベルのソフトローン、さらに政治上、最も決定的となったものが国民皆保険であった。これは初めて政党が公約とし、実行に移しさえした、計画的で普遍的な貧困・福祉対策計画であった。1997年に始まった景気の低迷が、エリートたちの力を弱めた。彼らの社会的対立に対する懸念は、彼らがタクシンと大衆たちとの政治取引に甘んじるに足るものであった。 TRTが並外れた人気を博したばかりか、有権者たちは、より対応力のある政府も可能であるという事に気が付いたのだ。これらの結果がエリートたちを動揺させた。王党派は国民選挙で選ばれた政治家たちを恐れ、タクシンを危険と見なしたが、これはタクシンが王室と張り合うような人気を確立させるかと思われたためである。2005年のタクシンの地滑り的再選を受け、枢密院議長のプレーム・ティンスーラ―ノンのような、王室寄りの人間は、君主制の政治的中心性が低下することを脅威と見た。この認識が、未だに終わらぬ選挙政治制限のための政治闘争を解き放つ事となった。保守派は、政治が最高の制度たる王制と共に機能すべきだという彼らの見解に、選挙が脅威になると考えた。彼らは選挙政治を、社会的、政治的秩序における王政の基本的役割を損ねるものと見なした。タクシンはまた、現状に異を唱えるにあたって官僚制度に揺さぶりをかけ、これを民選政治家や国民たちのニーズに答えるものとした。官僚たちの入れ替えや、諸大臣のリストラに際し、タクシンは自分のひいきの人物達を昇進させたが、この事は、数十年の間、国民たちを支配する事に慣れた高級官僚にとっては脅威であった。同様に、タクシンは資本家階級に挑み、国内のビジネスがより競争的なものとなる事を要求した。反対派はこれについて、シナワットの一団が競争力を得ていると考え、この経済力再編を危険であると考えたのだ。 タクシンは十分な自覚のないまま、エリート政治同盟である王室、軍部、企業に脅威を与え、また伝統的階級制を順守せぬ事で危険視される事となった。タクシンの下層階級への配慮は、数々の保守的、階層的、権威主義的諸勢力が、彼の政権に立ち向かう事を意味したのである。この結果が2006年のクーデターだ。クーデターは、この論争を終わらせはしなかった。赤シャツ派、その他のタクシン支持者たちが、王室と軍部に敵対したためである。2010年の新たな選挙を要求し、赤シャツ派は長期抗議行動を行ったが、その政治的レトリックは地位や不平等に的が絞られていた。 抗議者たちは周知の通り、被支配者である庶民を意味する古語、「プライ(phrai)」によって自分達を位置づけ、これに対する語として「アマット(amat)」、「支配階級の貴族」の語を用いた。彼らは法律の二重基準や、アマットたちの政治権力独占、さらには不平等に対して感じる深い憤りを強調した。赤シャツ派は急進的だという主張にも関わらず、彼らの要求は革新的であった。「我々が望む自由な資本主義国家は、金持ちと貧者の格差が縮小された国家である。我々は貧者のために、より多くの機会を作りたい。」という具合だ。この階級と地位に対する訴えがエリート層を怒らせたのは、特にこの抗議がサバルタンの団結を無視できぬ程にまで高めたためである。 この団結は政治動員と投票パターン、そして経済データの一致に反映されていた。投票パターンは低所得と貧困率に一致し、最貧困地域である北部と東北部、それに中央部の数県、さらにはバンコク周辺の労働者階級の暮らす地域で、一貫して親タクシン派政党への投票が行われた。平均的な一人当たりの県内総生産は、2007年にエリート層の支持する民主党に投票した県では、親タクシン派政党を支持する県に比べると、ほぼ2.4倍高かった。 不平等の政治 相対的に低い所得、歪んだ所有制、そして既存富裕層への所得の吸い上げ、これらが示すものは、長期的な搾取のパターンである。この搾取に対する抵抗はあったが、それらがこのパターンを変化させる事は無かった。エリート層は大抵、そのような「反逆」に、抑圧をもって応じてきた。この抵抗の結果、抗議者たちが1973年、1992年、2009年、そして2010年に、要求した通りに選挙政治がもたらされた際、その一つの結果となったのが恩顧主義の政治であり、これは文民政治家たちが不正で腐敗しているとの中傷を許容するものであった。この中傷が軍部や王室の干渉による抑圧や権威主義、エリート支配の再建を可能としている。エリート層は統治する際、その統治権を強調し、排他的概念である秩序や権威、道徳を引き合いに出す。このシステムの中心には、王政が不可欠であり、エリート層は王の道徳的権威と共に統治するという主張が存在する。 このイデオロギーを疑問視する者達が、繰り返し要求したのが、政治的代議制度と、深く根付いた搾取に挑む政策であった。中でも注目すべきは、選挙政治に対する粘り強い支持の存在である。2006年のクーデター以来、選挙が許されると、大勢の有権者たちが集まり、繰り返し、親タクシン政権への回帰が行われてきた。これは単なる親タクシン主義にとどまらず、選挙政治やサバルタンの利益を代表すると見られる政党の支持をも意味している。農村や労働者階級の有権者たちは、どうやら恩顧主義政治を拒み、あまり階級的でも搾取的でもない、より良い社会が築かれる事を望んでいるようだ。 赤シャツ派の多くの者たちにとって、民主主義はクーデターではなく、選挙政治を意味するようになった。また、不平等は裁判所から政治権力に及ぶ様々な舞台での「二重基準」と見なされた。正式の赤シャツ隊は「政治権力が真にタイ国民に属する」国家を要求したのである。彼らが望んだのは「公平で公正な国家」であり、「国民が貴族的寡頭政治(アマット)から解放され、誇りと自由と平等を有する」国家である。 これらの自由や正義、平等に対する要求は、政治体制の支配によって苦闘を経験してきた。このような要求への対応に、エリート層は司法手段を、軍部は銃を用いてきたし、王党派は度重なるデモを行ってきた。結果、2014年5月22日に軍事クーデターが生じ、これによって王党派エリート以外の政治家を弱体化させ、選挙政治を後退させようとしている。 結論 もし、トクヴィルが現在のタイにタイム・トラベルしたならば、彼は初期のアメリカ民主主義の特徴となり、その社会を構築していた「境遇の平等」を見出す事はできないだろう。むしろ、彼が目にする事になるのは、とてつもなく破壊的な、社会的、政治的、経済的制度の影響であり、これが不平等を維持すべく構築されている様子であろう。 Kevin Hewison西オーストラリア州 パース マードック大学 アジア研究センター 経営・管理学部(School of Management & Governance)Email: […]