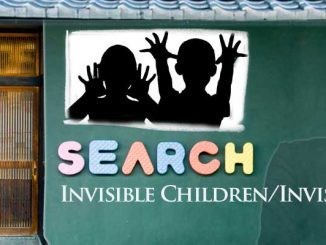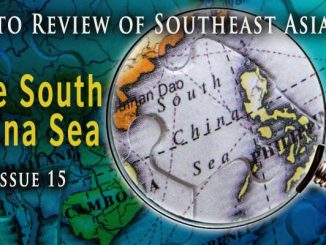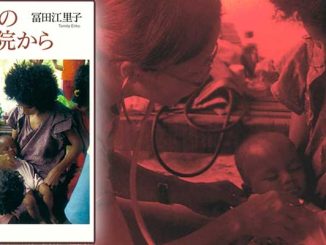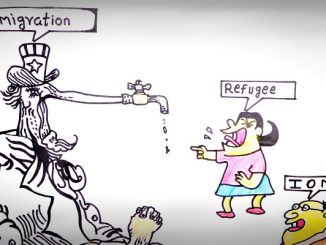漫画はインドネシアにおける最も重要な出版形式の一つである。翻訳された漫画出版物の初版は、その他全ての出版物よりも五倍(一作品につき15,000部)多い (Kuslum, 2007; Indonesia Today, 2012) 。日本の漫画の翻訳版がインドネシアで最もよく売れている本であり(Kuslum, 2007)、インドネシアで書かれて出版された漫画の数は、輸入された漫画の数に比べると少ない。 漫画出版社大手のElex Media Komputindo (EMK)は、毎月、日本漫画の翻訳本52冊に対し、現地の漫画1冊の割合で発刊している。もう一つの漫画出版社大手のM&Cによれば、彼らの出版物の70%が日本漫画の翻訳本である(Kuslum, 2007)。翻訳された日本の漫画の人気が高いのは、そのクロスメディア戦略にも依拠している。日本の漫画の人気が高すぎるので、インドネシア人たちの間では、現地の漫画を重視しようという動きも生まれている(Ahmad他、2005: 1, 2006: 5, 44–45; Darmawan, 2005)。全国紙Kompasの記事を見ても、或いは、DI:Y (Special Region: Yourself) 漫画展(2007)や、インドネシア漫画の歴史展(Indonesian Comics History Exhibition)(2011)といった展示会が開催されることからも、インドネシアの漫画を盛り上げようとする動きがあることが分かる。 インドネシアの読者たちは現地の漫画が持つニュアンスや、外国の漫画がそれぞれどう違うのか、という事がわかるようになってきている。読者たちがニュアンスの違いを理解できる理由の一つは、外国の漫画出版物が異なる時代に紹介されたからである。スーパーヒーローの漫画がアメリカから輸入されたのは1950年代であり、『タンタン』や『アストリックス』などの冒険漫画がヨーロッパから入ってきたのは1970年代であった。日本の漫画が市場に参入したのは、1980年代の終わりである。もう一つの理由は、それぞれの外国の漫画が特有の画風を持つことである。いくつかの出版物を見れば、また、漫画出版の慣例を見てみると、こうした二つの要因が組み合わさって、漫画の分類が行われていることが分かる(Ahmad他、2005, 2006; Giftanina, 2012; Darmawan, 2005)。そして、読者や出版社、漫画家たちは、現地のある漫画を取り上げて、これはある外国のスタイル(gaya)で描かれていると述べたりするのである。 このスタイル(インドネシア語でgaya)とは、画風のことである。インドネシアの漫画論で、gayaと言えば、登場人物の描写や、コマ割、テーマなど、視覚的なステレオタイプに関する要素を指す。分かりやすい例としては、日本漫画(マンガ)の大きな瞳をした登場人物、写実的な筆致のアメリカのスーパーヒーロー漫画、ヨーロッパ漫画に用いられるリーニュ・クレール(ligne Claire/明晰な線)などである(Giftanina, 2012; […]