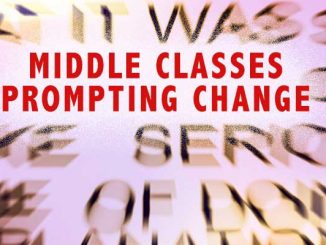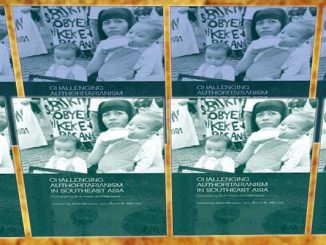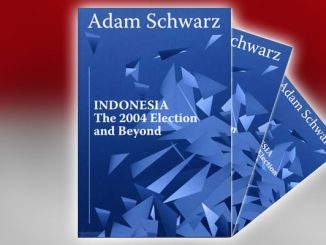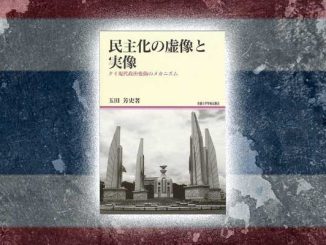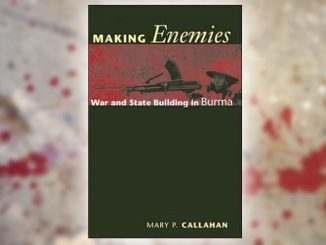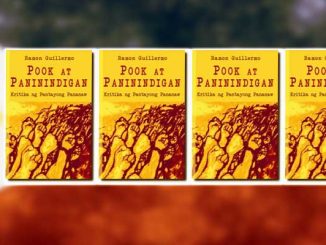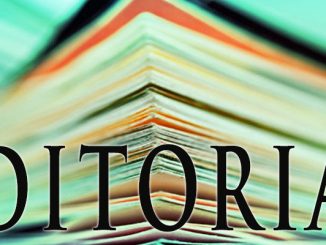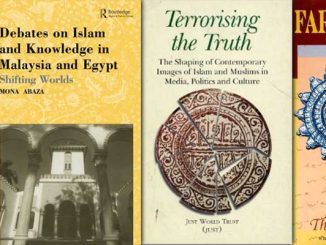แล้วพบกันใหม่ ผมเดินทางไป ๆ มา ๆ ยังประเทศอินโดนีเซียตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และตลอด12 ปี ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ศึกษาวิจัยในสาขามนุษยวิทยาทางวัฒนธรรมในเมืองย็อกยาการ์ตาบนเกาะชวา ผมกลับมาที่นี่อีกครั้งในฤดูร้อน ค.ศ.2002 เพื่อนเก่าผู้หนึ่งที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนที่รู้จักเป็นส่วนตัวได้แวะมาเยี่ยมบ้านทางตอนใต้ของเมืองย็อกยาที่ผมและครอบครัวพำนักอยู่ มาส ยาร์โต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดูแลรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยเลี้ยงให้กับโครงการวิจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในย็อกยา เคยช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับโครงการวิจัยในลักษณะคล้ายคลึงกันในสมัยที่ผมได้พบเขาครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อน ตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกเดินทางมากับภรรยาของผม ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกเช่นกัน เราทั้งสองกำลังวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกในสาขามานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมในเมืองย็อกยาแห่งนี้ ในคราวนี้เมื่อผมกลับมา มาส ยาร์โต และผมทักทายกันอย่างกระตือรือร้นด้วยการจับมือ และหอมแก้ม หลังจากที่มาส ยาร์โต ถอดรองเท้าออกแล้ว เขาก็เดินผ่านเข้ามาในห้องเล็ก ๆ ทางด้านหน้าของบ้านที่เปิดออกสู่ห้องรับแขกที่มีขนาดกว้างขวาง ห้องรับแขกนี้มีพัดลมติดเพดาน และตกแต่งด้วยวัตถุโบราณของชวา สิ่งทอ และศิลปะสมัยใหม่ของอินโดนีเซีย ในมุมหนึ่งของห้องที่มีพื้นเป็นหินอ่อนนี้ มีรูปภาพสีน้ำที่งดงามภาพหนึ่งแขวนอยู่ ภาพนี้เป็นภาพของบุรุษนายหนึ่งที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่อยู่ในเสื้อแขนสั้น และสวมหมวกสีดำที่ชินตา คือ ซูการ์โน ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย ในท่ามกลางวัตถุต่าง ๆ ที่ชวนให้ระลึกถึงบรรยากาศแห่งความเป็นสมัยใหม่เหล่านี้ ในขณะที่พัดลมหมุนไปมาอยู่บนเพดานให้เสียงชวนฟัง ผมและเพื่อนชาวอินโดนีเซียก็สูบบุหรี่สำราญกับควันที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพ ไม่นานนักบทสนทนาของเราทั้งสองก็วกไปที่เหตุการณ์ 9/11 ดวงตาของมาส ยาร์โต ดูเหมือนจะเพ่งทะลุม่านบาง ๆ จากควันกานพลูหอมกรุ่นเขาเสนอทฤษฎี และคำถามที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โศกนาฎกรรมครั้งนั้น เขาจ้องตรงมาที่ตาของผม ขณะที่ถามว่า “เป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่คนยิวนับพัน ๆ คนที่ทำงานที่ตึกเวิรลด์ เทรด เซ็นเตอร์ รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น และไม่มาทำงานในวันนั้น” จึงไม่ต้องเผชิญกับความวุ่นวาย การบาดเจ็บ และล้มตาย คำถามที่มีคำตอบอยู่ในตัวนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า “พวกยิวเป็นพวกที่ขับเครื่องบินชนตึก” ในขณะนั้นเอง เราได้ยินเสียงบ่งบอกถึงเวลาสวดมนต์เย็นที่เริ่มดังก้องไปทั่วเมือง แล้ว มาส ยาร์โต ซึ่งกำลังทำทีประหนึ่งว่าข้อสรุปที่เขาเสนอมาสักครู่นั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ ก็ขอตัวอย่างสุภาพออกไปล้างมือ ล้างเท้า ล้างหน้า และเลี่ยงออกไปสวดมนต์ในมุมหนึ่งของห้องนี้ ในขณะที่ผมก็สูบบุหรี่ต่อไปในความเงียบงัน เช่นเดียวกันกับ มาร์ค เพิร์ลแมน ที่กลับมาที่โซโล ซึ่งเป็นอดีตเมืองราชสำนักอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของย็อกยา ในปี คศ.1997 ผมรู้สึกว่า “ผู้คนที่นี่มีความเสื่อมใสและเคร่งครัดในศาสนามากยิ่งขึ้น”อย่างเห็นได้ชัดเจน (เพิร์ลแมน [Perlman]1999, 11) ตลอดเวลาที่เราได้รู้จักกันมา ครั้งเดียวที่มาส บาร์โต สวดมนต์ต่อหน้าผม คือ ตอนที่เขาอยู่กับเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งในห้องเล็ก ๆในสำนักงานที่จัดไว้ให้เป็นห้องสวดมนต์ ผมเคยไปพักค้างคืนที่บ้านของเขาหลายครั้งหลายหน และเราใช้เวลาช่วงบ่ายหลังเลิกงานด้วยกันขี่มอเตอร์ไซด์ของเขาตระเวนเที่ยวทั่วเมืองบ้าง ดูภาพยนตร์บ้างเป็นครั้งเป็นคราว และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ร้านขายอาหารแผงลอย และสถานที่อื่น ๆ ทั้งใน และรอบ ๆ ย็อกยาที่มาส ยาร์โต เห็นว่าผมควรจะรู้จัก บทสนทนาของเราในวันเก่า ๆ นั้น ส่วนมากว่าด้วยการเมือง วัฒนธรรม วัฒนธรรมชวา และการรักษาแผนโบราณที่ผมสนใจในขณะนั้น แม้ว่าเขาพำนักอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ทางใต้ของย็อกยา ซึ่งเป็นที่ฝังศพของอดีตผู้นำและครอบครัวที่เคยปกครองเมืองโซโล และย็อกยาซึ่งเป็นเมืองราชสำนักเก่า (สำหรับชาวอินโดนีเซียแล้ว จะถือว่าหลุมผังศพเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีพลังลึกลับ) แต่เราก็ไม่เคยพูดถึงความหลากหลายทางศาสนาของชวา หากจะพูดถึงบ้างก็มีแต่เรื่องของการใช้ความลึกลับทางศาสนาของชาวชวาในการบำบัดรักษา เท่าที่ผมจำได้ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ไม่เคยเป็นหัวข้อการสนทนาของเราเลย ในช่วงแรก ๆ ที่เรารู้จักกัน ผมพบว่า มาส ยาร์โต เป็นคนที่มีความเป็นสมัยใหม่ เขานิยมซูการ์โน และไม่ไว้วางใจแนวทางของซูฮาร์โตที่ว่าด้วยการสร้างระบบใหม่ เขาสนใจวิทยาศาสตร์ แม้จะเป็นแบบที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลระดับล่างเช่นเขาจะเข้าใจได้ และเขาก็ผูกมิตรกับผมซึ่งมาจากประเทศ ซึ่งในขณะนั้นเป็นตัวแทนของทุกอย่างที่ทันสมัยตั้งแต่เทคโนโลยีจนถึงเพศสัมพันธ์ บ่ายวันหนึ่งเราสองคนและเพื่อน ๆ จากที่ทำงานไปดูภาพยนตร์เรื่อง JFK ของโอลิเวอร์ สโตน ด้วยกัน ตอนที่เควิน คอสต์เนอร์ดารานำเริ่มเล่าว่า แผนการสมคบคิดที่เขาเสนอนั้นนำไปสู่เหตุการณ์การลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์น เอฟ เคนเนดี้ได้อย่างไร ผมสังเกตเห็นว่าดวงตาของมาส ยาร์โต เอ่อไปด้วยน้ำตา หลังจากจบภาพยนตร์ ยาร์โตและเพื่อน ๆ เห็นพ้องว่า จอห์น เอฟ เคนเนดี้ และซูการ์โน มีลักษณะหลาย ๆ อย่างคล้ายกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นกับเคนเนดี้ในภาพยนตร์ก็เกิดขึ้นกับซูการ์โนเช่นกัน นอกจากเรื่องทฤษฎีสมคบคิดแล้ว ก็มีเรื่องของการวิพากษ์รัฐชาติสมัยใหม่ และเจตน์จำนงของรัฐบาลที่เราสนใจร่วมกัน หัวข้อเหล่านี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นสมัยใหม่ที่ดุเดือดเอาการทีเดียว คราวนี้ในปี คศ.2002 เราหวนกลับมาถกประเด็นทฤษฎีสมคบคิดกันอีกครั้ง ในท่ามกลางเสียงเรียกให้สวดมนต์เย็นที่ดังก้องไปทั่ว มาส ยาร์โต เสนอข้อโต้แย้งของเขาทีละประโยค ๆ อย่างมั่นใจ โดยความคิดเหล่านี้มีรากฐานจากขนบที่เชื่อว่ามีผู้สมคบคิด และผู้ก่อการอยู่เบื้องหลัง ในทุก ๆ ฉากของประวัติศาสตร์ ทุก ๆ ย่างก้าวที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เริ่มต้นขึ้นใน ค.ศ.1997 ตามมาด้วย การล่มสลายของรัฐบาลที่มีซูฮาร์โตเป็นผู้นำ การลุกฮือขึ้นมาต่อสู้อย่างรุนแรงในส่วนต่าง ๆ ของหมู่เกาะอินโดนีเซียการประท้วงของนักศึกษา ขบวนการปฏิรูปที่มีชื่อว่า Reformasi เรื่องฉาวโฉ่ที่เกี่ยวกับธนาคาร การฆ่าหมอผีที่เล่นคุณไสย การข่มขืนสตรีเชื้อสายจีนและที่มีเลือดผสมระหว่างจีนและอินโดนีเซีย และขบวนการล่าหัวมนุษย์ใหม่ในหมู่เกาะรอบนอก ไปจนถึงการเมืองของรัฐบาลทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ยืนยัน และประโคมข่าวว่ามีคนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลายาวนาน และผมรู้สึกว่า มาส ยาร์โต มีความเป็นคนสมัยใหม่ ผมจึงอธิบายให้เขาฟังอย่างมุ่งมั่นว่าข้อสรุปเช่นนี้ไร้สาระเป็นอย่างยิ่ง ผมกล่าวอย่างไม่ลังเล (และไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำไป) ว่ามีหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งยืนยันว่าสมาชิกขบวนการอัลเคด้าของโอสะมา บิน ลาเดน เป็นผู้วางแผนอยู่เบื้องหลัง และเป็นผู้ดำเนินการโจมตี ตลอดช่วงฤดูร้อน ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าผลกระทบของเหตุการณ์ เช่น 9/11 ที่แผ่กระจายไปทั่วโลก ได้เขามามีบทบาทในความสัมพันธ์ของผมกับมาส ยาร์โต ตั้งแต่ที่ผมมาถึง เขาได้แสดงความสนใจอย่างล้นเหลือที่จะชวนเชิญให้ผมหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ และลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลามในเกาะชวา เขาถึงกับกุลีกุจอจัดการนัดสัมภาษณ์ให้ผมได้พูดคุยกับผู้คนที่เขาและเพื่อน ๆ เของเขาในเมืองนี้เห็นว่าเป็นปราชญ์ทางศาสนาอิสลามที่รอบรู้ ครั้งหนึ่งผมได้พบกับบุคคลสำคัญในท้องถิ่นท่านหนึ่งที่ได้ศึกษาคำสอนและการปฏิบัติของศาสนาอิสลามด้วยตนเอง โดยการพบปะครั้งนี้จะมีขึ้นที่เมืองที่พำนักของ มาส ยาร์โต ซึ่งอยู่ทางใต้ของ ย็อกยาออกไปประมาณชั่วโมงครึ่ง มาส ยาร์โต ได้เชิญเพื่อน ๆ จากย็อกยาร่วมฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย และเนื่องจากเราจะพบกันในตอนค่ำ มาส ยาร์โต จึงจัดการให้เพื่อน ๆ ของเขามารับผม และขับรถพาผมไปยังที่นัดผม ในขณะที่ผมรอพวกเรามารับ จู่ ๆ ผมก็นึกถึงภาพในหนังสือพิมพ์ของ เดเนียล เพิร์ล ผู้สื่อข่าวที่ถูกฆ่าตาย ขณะถูกมัดอยู่กับพื้นศีรษะก้มต่ำ ผมถูกกระชากเป็นกระจุกอยู่ในมือของผู้จับกุมที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในภาพ และมีปืนและมีดจ่ออยู่ที่ศีรษะ เป็นเรื่องที่น่าอายจริง ๆ ที่ผมจะต้องเล่าว่า ผมกลัวมากจนกระทั่งในระหว่างที่รอยู่นั้น ผมเดินกลับไปที่บ้านเพื่อบอกภรรยาของผมว่าหากผมไม่กลับมา ขอให้เธอเข้าใจว่าอาจมีอันตรายเกิดขึ้นกับผม ทั้ง มาส ยาร์โต และผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในบรรยากาศแห่งความขัดแย้งทางอัตลักษณ์ที่ถูกแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา สามารถกลายเป็นคนที่กระทำการรุนแรงอย่างมากได้ “ความหลากหลายแห่งความเป็นจริงในรูปแบบต่าง ๆ” ที่ผมนำเข้ามาในจินตนาการของผม ทำให้ผมประหวั่นพรั่นพรึงได้อย่างน่าประหลาดใจทีเดียว เท่าที่ผ่านมา ตลอดเวลาที่ผมอยู่ในประเทศอินโดนีเซียผมไม่เคยรู้สึกกลัวเช่นนี้มาก่อนเลย ยิ่งกว่านั้นความกลัวนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ผมถือว่าเป็นเพื่อน และญาติสนิทคนหนึ่ง เราทำงาน รับประทานอาหาร เดินทาง และสนุกด้วยกัน ผมส่งเสียให้ลูก ๆ ของเขาได้เรียน เขาให้ความช่วยเหลือในงานของภรรยาผม มิตรภาพที่ผมและเขามีต่อกันนั้นเหนียวแน่นพอ ๆ กับ ที่ผมมีให้เพื่อนคนอื่น ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย หรืออาจจะมั่นคงกว่ากับคนอื่น ๆ ก็ว่าได้ ความกลัวที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งที่จริงเป็นความรู้สึกที่ผูกกับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ที่ผมประสบอยู่ขณะที่ผมก้าวเขาไปในรถตู้ขนาดเล็กที่มารับผมนั้นบั่นทอนความรู้สึกผูกพันทางใจในมิตรภาพของเราสองคน ที่แม้จะเป็นความผูกพันที่ยั่งยืน แต่อันที่จริงก็กำลังพัฒนาและแปรเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ในขณะนี้ผมนึกสงสัยขึ้นมาว่า ในเหตุการณ์นั้น ผมควรจะบอกให้ มาส ยาร์โต ทราบถึงความกลัวของผมก่อนที่ผมจะกลับบ้าน หรือไม่และสองปีให้หลัง (คศ.2004) เราพบกันสั้น ๆ อีกครั้งหนึ่งเราพบว่าเราไม่มีอะไรจะพูดกันสักเท่าไร แม้ว่า มาส ยาร์โต จะนำของที่ระลึกมาให้ผม ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์แทนประเทศอินโดนีเซียในยุคปัจจุบัน (ทั้งนี้ โมต และรูเธอร์ฟอร์ด ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของเกาะปาบัว ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน “การเสนอภาพความรุนแรง[และเรื่องราวอื่น]) ที่ผ่านการแทรกแซงของสื่อนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น” (โมต และรูเธอร์ฟอร์ด [Mote and Rutherford] 2001, 117) มาส ยาร์โต นำหนังสือมาให้ผมหนึ่งเล่ม และแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้เป็นภาพของความรุนแรง ผมกลับรู้สึกเสมือนว่ามันรวบรวมการแปลความที่หลากหลาย การเขียนขึ้นใหม่ และความเป็นจริงเสมือนที่เข้ามามีอิทธิพลต่อจินตนาการของเราอย่างท่วมท้นในยุคนี้ หนังสือเล่มนั้น คือ งานตีความพระคัมภีร์อัลกุรอาน ของนักวิชาการตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฉบับแปลภาษาอินโดนีเซีย การแทรกแซง หลังจากวิกฤตการเมือง และเศรษฐกิจ ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล เหตุการณ์ 9/11 และสงครามในประเทศอัฟกานิสถาน และอิรัก นานาประเทศตั้งความหวังไว้ประการหนึ่งกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรที่เป็นมุสลิมจำนวนมากที่สุดในโลก ความหวังนั้น คือ ขอให้ประชาชนและการเมืองของประเทศคง “ความเป็นกลาง”ต่อไป เป็นที่เข้าใจกันดีในหมู่ ผู้ศึกษาประเทศอินโดนีเซียว่า ประวัติศาสตร์ที่หนักแน่นยาวนานของความใจกว้างยอมรับความแตกต่างและความยืดหยุ่นต่ออัตลักษณ์ และชีวิตทางสังคมที่พบได้ในผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเมืองเชิงอัตลักษณ์ที่มีความเป็นกลาง อันที่จริงผู้คนมักจะพูดถึงความใจกว้าง และความยืดหยุ่นของทัศนคติ และวิถีชีวิตว่าเป็นลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหมู่เกาะอินโดนีเซีย ในการอธิบายให้เห็นลักษณะเด่นที่เป็นจุดยืนทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ โอ ดับเบิลยู โวลเตอร์ (O. W. Wolters)อ้างจากหลักฐานภาษาชวาในศตวรรษที่ 19 ชิ้นหนึ่งถึงลักษณะร่วมหนึ่งที่บุคคลจากสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ พึงมีเหมือนกัน นั่นคือ คนที่เจริญแล้ว (wong praja) จะเป็นคนที่ยืนหยุ่น (lemesena) (1999, 161) เบเนดิค แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า สำหรับชาวชวาแล้ว “เขาจะอดทนยอมรับแทบทุกอย่าง หากสิ่งเหล่านั้นสามารถนำมาปรับ หรืออธิบายให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวชวาได้” แต่กระนั้นเมื่อไม่นานมานี่เอง แอนเดอร์สันมองย้อนกลับไปในอดีต และชี้ให้เห็นว่า ขณะนี้ “ความใจกว้างของชาวชวา” ลดน้อยลงไป และสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เห็นในสังคมทั้งในเชิงสัญลักษณ์ และในเชิงรูปธรรมในหลาย ๆ กรณี คือ การก่อตัวขึ้นของ“กำแพงสูงใหญ่ที่ขวางกั้นไม่ให้กลุ่มคนที่แตกต่างกันมาพบกันได้” เหตุการณ์ต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งก่อนและหลังโศกนาฎกรรม 9/11 ชี้เป็นนัยให้เห็นว่า ความใจกว้าง และความสามารถของชาวชวาที่จะ “เปลี่ยนที่ไปมา” ในประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้กำลังถูกท้าท้ายอยู่ ยิ่งกว่านั้นแล้ว “ความเป็นพลเมืองที่ยืดหยุ่นและลื่นไหล” มาโดยตลอดที่ยอมรับทั้งศาสนาที่นับถือ และความเป็นบุคคลนั้นดูเหมือนว่ากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การขาดความผ่อนปรนที่ปรากฏมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่เราเคยชินมากไปเสียแล้ว ดังที่แอนเดอร์สัน (Anderson) แสดงความรู้สึกเศร้าสลดไว้เมื่อประมาณ 40 ปีก่อน และอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้ อิทธิพลต่าง ๆ จากเหตุการณ์ในโลก และการก่อตัวขึ้นของลัทธิชาตินิยมในหมู่ชาวชวา “เข้ามาคุกคามความหลากหลายทางศีลธรรมเดิม ๆ อย่างเห็นได้ชัด” และ “บั่นทอนความใจกว้างยอมรับความแตกต่างที่เป็นลักษณะเดิม ๆ ซึ่งโครงสร้างทางสังคมกำหนดให้ดำรงอยู่” (1996, 42) จากการสังเกตและการสนทนาทั้งอย่างใกล้ชิดและจากที่มองอยู่ห่าง ๆ ณ ที่นี้ผมต้องการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปของอัตลักษณ์ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตลักษณ์ทางศาสนา ซึ่งสังเกตเห็นได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้ว่าปัญหาความขัดแย้งท้องถิ่นใน มาลุกุ กะลิมันตัน และสุลาเวสี ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ หรือหลายมิติรวมกันนั้นอาจเป็นตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างยอมรับความแตกต่างที่ลดน้อยลง และการสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่ยืดหยุ่นและตายตัวมากยิ่งขึ้น แต่ในที่นี้ผมขอเลือกศึกษาจากบทสนทนากับมาส ยาร์โต เพื่อนเก่าของผมผู้นี้ และเพื่อนคนอื่น ๆ ระหว่างที่ผมเข้าไปเก็บข้อมูลที่ย็อกยาการ์ตา และบริเวณใกล้เคียง ใน คศ.2002 เป็นที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งที่ผมได้เผชิญหน้ากับ “ยิว” หรือ Yahudi เป็นครั้งแรกในภูมิภาคท้องถิ่นที่ผมคุ้นเคยนี้ เมื่อผมเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น ผมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัญญะซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั้นนอกจากจะมีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นสัญญะพิเศษที่ช่วยในการตีความเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ 9/11 และเหตุการณ์อื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศอินโดนีเซียแล้ว สัญญะนี้ยังอัดแน่นด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบและการปฏิบัติทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทวิลักษณ์ในการสร้างอัตลักษณ์ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อพิจารณาจำนวนของชุมชนชาวยิวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีอยู่น้อยมาก ก็น่าจะบอกได้ว่าความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับชาวยิวก็มีอยู่น้อยมากเช่นกันในหมู่ชาวอินโดนีเซีย นอกจากนั้นแล้ว ชาวยิวจำนวนน้อยนิดที่อยู่ในชุมชนเล็ก ๆ ที่สุราร์บายาไม่เคยเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์หรือต้องประสบกับการแบ่งแยกสีผิวที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศเมื่อไม่นานมานี้เลย เพื่อนบ้านชาวมุสลิมทักทายชาวยิวอย่างเป็นมิตรด้วยการกล่าวคำว่า “ซาโลม” อาหารของชาวยิวก็มาจากเนื้อที่พ่อค้าเนื้อฮาลาลชาวมุสลิมเป็นผู้ตระเตรียมให้ และในทศวรรษที่ผ่านมา ครอบครัวชาวมุสลิมรับหน้าที่ดูแลโบสถ์ยิวเล็ก ๆ ที่อยู่ในชุมชนนั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียนี้บอกเป็นนัยว่า สัญญะของ “ชาวยิว” ในประเทศอินโดนีเซียนั้นได้รับการตีความที่สอดคล้องกับเหตุการณ์อื่น ๆ และความกังวลในหมู่ชาวอินโดนีเซีย ตัวอย่างเช่น หลังจากการเลือกตั้งรัฐสภาของนายดับดูร์ราห์มัน วาห์ฮิด ประธานาธิบดีคนที่ 4 ของประเทศอินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียเริ่มรู้สึกว่าความรุนแรงของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เป็น “เรื่องของที่อื่นที่ถูกแทรกแซง” ในช่วงเวลานี้เองที่ “ยิว” ในฐานะที่เป็นสัญญะทางการเมืองได้เข้ามามีบทบาทในประเทศอินโดนีเซีย ผู้คนรับรู้สัญญะดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ตามสื่อต่าง ๆ ว่า คือ ความเป็นจริง ซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นเมื่ออยู่ในบริบทของสัญญะตัวอื่น ๆ ที่สื่อความให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้พอ ๆกัน เฟลด์แมน (Feldman) (2000) อธิบายว่า การปรากฎให้เห็นของสัญญะเหล่านี้ในบริบททางการเมือง เป็น “ระบบในทางการมองเห็น”/”จักษุระบบ” โดยที่ในระบบนี้ “ความหลากหลาย” ของสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นจริงรูปแบบต่าง ๆ” เข้ามากำหนดความเข้าใจต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์ (โปรดดู เฟลด์แมน [Feldman] 2000) ซีเกลตั้งข้อสังเกตว่า“คำว่า ‘ยิว’ ในประเทศอินโดนีเซียบ่งบอกถึงภัยคุมคาม” แต่เป็นภัยคุกคามที่ไม่มีรูปร่าง (2001, […]