
Celebrating Muhammad’s Birthday in Yogyakarta
The festival of the birth of the Prophet in Indonesia begins on the sixth day of the month of Mawlid and ends on the twelfth day. It is one of the most important religious festivals […]

The festival of the birth of the Prophet in Indonesia begins on the sixth day of the month of Mawlid and ends on the twelfth day. It is one of the most important religious festivals […]

Amidst a wave of recent studies on the global decline of democracy and the concurrent resurgence of authoritarianism (Diamond 2008; Diamond 2015), the Thai case stands out because unlike authoritarian regimes elsewhere, Thailand since May […]

This year saw the premiere of Itumba ang mga Adik (Kill the Addicts) in the Philippines. Shot in streets across the country, from narrow alleys to cramped rooms, the controversial film stars vigilantes, (suspected) drug […]
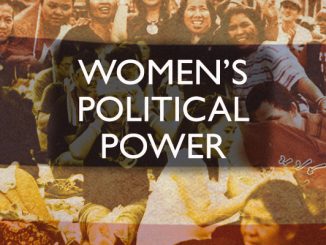
This article derived from a dissertation entitled “Women’s New Political Space in Thailand: A Case Study of the Red and Yellow Shirt Movements”, which set out to explore the extent of women’s participation in the […]

The Internet led to exciting claims and predictions about how it could change the world, one area of which was in terms of democratisation. Academics in the 1990s predicted that with its decentralized, uncontrolled and […]

Reports and images broadcast in international news media on the “the refugee crisis” and particularly the exodus of Syrian men, women, and children escaping their country’s civil war over the past several months have elicited […]

Siaran laporan dan gambar di media berita internasional tentang “krisis pengungsi” dan khususnya pelarian penduduk Suriah pria, wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari perang sipil yang terjadi di negara mereka selama beberapa bulan terakhir […]

รายงานและภาพที่ถ่ายทอดในสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับ “วิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัย” โดยเฉพาะการอพยพครั้งใหญ่ของชายหญิงกับเด็กชาวซีเรียที่หนีจากสงครามกลางเมืองในประเทศของตนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้หวนนึกถึงความทรงจำเกี่ยวกับการหนีออกนอกประเทศครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้ว เมื่อชาวกัมพูชา ลาวและเวียดนามหลายแสนคนละทิ้งประเทศของตนภายหลังคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะใน ค.ศ. 1975 ลักษณะคู่ขนานระหว่างการอพยพสองครั้งนี้เห็นได้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการเดินทางอันน่าหวาดหวั่นที่ต้องลอยเรือกลางทะเลเพื่อขึ้นฝั่งในยุโรปหรือเอเชีย การอพยพย้ายถิ่นด้วยความจำใจทุกครั้งย่อมมีพลวัต ต้นตอและผลกระทบที่เป็นลักษณะเฉพาะของมันเอง มันอาจมีลักษณะคู่ขนาน แต่ไม่มีทางเหมือนกันโดยสิ้นเชิง กระนั้นก็ตาม มีเรื่องเล่าทับซ้อนกันสองชั้นที่ครอบทับการอพยพหนีออกจากประเทศทั้งสองระลอกข้างต้น ในด้านหนึ่ง เรื่องเล่านำเสนอภาพเหยื่อ “โลกที่สาม” ที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งคือ (ความพยายาม) ปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากประเทศ “โลกที่หนึ่ง” Yen Le Espiritu ตำหนิงานเขียนเชิงวิชาการก่อนหน้านี้ที่มองว่าผู้ลี้ภัยชาวเวียดนาม “เป็นแค่วัตถุของการช่วยเหลือ วาดภาพว่าพวกเขาโศกเศร้าจนช่วยตัวเองไม่ได้ ดังนั้น พวกเขาจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล โดยอ้างว่าการดูแลที่ดีที่สุดทำได้ในและโดยสหรัฐอเมริกาเท่านั้น” (Espiritu 2006: […]

国際報道機関の伝える「難民危機」に関する報道や映像、とりわけ、シリア人の男女、子供達が母国の過去数か月におよぶ内戦を避け、大移動する様は、もう一つの大規模な逃亡の記憶を呼び起こす。それは40年程前に何十万人ものカンボジアやラオス、ベトナムの人々が、1975年の共産主義の勝利の結果、国を後にした記憶である。この二つの大移動の類似点は見過ごし難く、最も顕著なものは、彼らがすさまじい海路の旅でヨーロッパやアジアの海岸へ辿り着こうとする点である。あらゆる強制移住には、それなりの原動力や発端、結果がある。すなわち、類似点を引き出す事は可能であっても、それらは同一ではない。だが、いずれの逃亡にも顕著な二重のナラティブの特徴は、一方に無力な「第三世界」の犠牲者たちがいて、もう一方には「第一世界」による人道救助活動(計画)があることだ。ベトナム人難民に関して言えば、Yen Le Espirituが酷評した先行学術論文は「(彼らを)救助の対象」と位置づけ、「彼らを悲嘆のために無能力状態に陥った保護が必要な者として描き、その保護はアメリカで、またアメリカによって最良のものが提供されるという事だ」(Espiritu 2006: 410)。このナラティブはおそらく、多くの新聞やテレビの「ボート難民」の苦難や難民キャンプでの人道問題の報道に影響されたもので、これが転じて「インドシナ難民」に関する集合的記憶を形成した。 事実、後者に付随する言説やイメージがあまりにも揺るぎないものであるために、彼らを「人工記憶」保有者と呼んでも見当違いにはならないだろう。Alison Landsbergの概念は、これらの出来事を生き抜いた経験を持たない人々の心を動かす「新たな形をした公的文化的記憶」に関連している。これらの記憶は「実体験の産物」ではなく、Landsbergが述べるように、「媒介表現に接する(映画を見る、博物館を訪れる、テレビの連続ドラマを見る)事から生じた」記憶なのである(Landsberg 2004: 20)。2015年に賞を獲得した双方向的なグラフィック・ノベル、『ボート(The Boat)』は、Nam Leのアンソロジーのタイトルとなった短編作を脚色したもので、このような記憶のテクノロジーと大衆文化の一例である。この作品はオンライン読者のみを対象に制作され、心を揺さぶるよう、本文と画像、音声と動きを融合させ、一人のベトナム人の少女が両親によって難民ボートに乗せられ、オーストラリアへ送り出された物語を伝える。 この「捨て身で救助される」というナラティブは、戦争と暴力の犠牲者としてのインドシナ人難民のイメージを具体化している。難民として、歴史の犠牲者としての立場が認識されているため、当然、難民達には何の術もなく、その亡命生活は彼らが救助されてホスト社会に入るその日に始まるかのように思われている。逆に、彼らが母国を発った時の状況や事情がつぶさに調べられる事は希である。だが彼らの人生の決定的瞬間は、彼らが桁外れに困難な状況を抜け出す事を決意した際の、彼ら自身のイニシアティブの結果なのである。筆者は2015年にシドニー郊外で、1975年以降にラオスを去ったラオス系オーストラリア人達にインタビューを行った。推測では、約40万人のラオス人が1975年から1980年代の後期までに(主に)フランスやカナダ、アメリカ合衆国、オーストラリアに逃げ込んで亡命した。ラオス国民の大移動は、ベトナム人やカンボジア人の大移動のようには知られていない。この理由はおそらく、これが前者の規模に相当するものでもなければ(約175万人のベトナム人が1975年から1990年代半ばまでの間に国から逃亡した)、カンボジア人生存者たちのような極度のトラウマを特徴とするわけでもなかったという事だ。 ラオス人難民の逃亡理由を述べる際、報道は通説を繰り返す。「一部のラオス人たちは再教育収容所に入れられる事を恐れて逃亡した。他の者達が出て行った理由は、政治的、経済的、宗教的な自由を喪失した事である」というものだ(UNHCR 2000: 99)。これらの要因や事情は、概ね正しいのであるが、これらの説明には亡命者達のプロフィールや体験を均質化する傾向があり、まるで彼らが年齢や性別、あるいはエスニシティに関わらず、同一の必要に迫られて一様な集団を形成したかのようなのだ。筆者がインタビューの対象としたのは、ラオス系オーストラリア人で、1960年代初頭から1970年代後期に生まれた人々である。筆者が調査を試みた集団が、歴史的な出来事、すなわち、政治体制の崩壊と社会主義者の支配の出現、そして大量脱出を、人生のほぼ同時期、子供時代から成人期にかけて生き抜いた人々であったからだ。若いラオス人難民たちは重要であるにもかかわらず、見過ごされた集団であったのだ。1975年以降にラオスから逃げ、1975年から1987年の間にタイのキャンプを通過した人々の約40%は13歳から29歳であった(Chantavanich and Reynolds 1988: 25)。 共産主義の勝利に続く時代の記憶は、ラオスにおける厳しい生活環境を描く。設立当初から、新政権は存続を懸けた戦いを行っていた。彼らはアメリカの空爆によって破壊された国家の再建という、途方もない課題に直面していたのである。1975年以降、西洋諸国の大半は支援をやめるか、その援助を大幅に削減した。隣接するタイが通商を禁じた事が、経済を苦境に陥れた。さらに、一連の自然災害(1976年の干ばつ、1977年と1978年の洪水)は、農業生産を著しく妨げた。日常生活は一層束縛され、国内の移動が制限されて、日常的な監視は強化された。SomchitとVilayvanhは当時、十代後半であった。二人共、ビエンチャンに住んでいた。Somchitは数年前に学校を卒業し、運転手として働いていた。Vilayvanhは大学生であった。Somchitは首都ビエンチャン近郊の村に育ち、1975年には19歳であった。彼はその頃結婚したてで、妻と共に彼の雇い主がビエンチャン郊外に用意した家に引っ越したばかりだった。Somchitは成人期を目前に、彼の周囲で世界が崩壊していく様を目にしたのである。彼が記憶していたのは、「物事が不安定(voun)になり」、「混沌(voun vai)としてきた」事であった。同じ時期、彼の妻は二人の赤ん坊を死産させている。「私の人生は行き詰ってしまった(bor mi sivit lort)」。彼が出て行ったのは1978年で、メコン川を泳いでタイに渡った。彼の妻は彼女の両親と共に留まる事を選んだ。Vilayvanhは南部のチャンパサック県の村で育ち、彼女がビエンチャンのロースクールの二年生であった1974年は、Somchitと同じ言葉を用いれば、「事態が混沌としてきた(voun vai)時代であった。彼女は学位を取得する事ができず、1975年以降は医学の道に転じた。彼女は1990年まで国を出なかった。 SomchitとVilayvanhの話は、両者が「混沌とした」、「不安定な」と表現したこの時代の記憶について、同様の圧倒的な不安感を伝えていた。彼らのナラティブは、特定の歴史的時期の中で、個人的な体験や彼らの周囲の人間、つまり家族や仲間たちの体験を介して形成されたものである。SomchitとVilayvanhは、歴史的出来事の主観的体験の共有によって定義される世代コホートに属している。これはカール・マンハイムが「連関世代(generation as actuality)」と名付けたもので、特定の生涯の一時期における「歴史的問題」の集団的体験が、解釈や内省によって結び付けられる方法である((Mannheim 1952: 303)。Thomas Burgessの社会変動の時代における青年期の定義も、これが安定した「伝統的」社会からの決裂の重要性を強調するために有用である。彼の言葉によると、「断絶がより決定的である場合、(…)青年期はライフサイクルの中の一時期としてよりもむしろ、歴史的コホートとして出現し」、それは「その世代を前後の別世代から隔て、一段と多くの交渉や変動、創作の余地がある特有の歴史的背景やナラティブ」によって定義されている(Burgess 2005: x)。言い変えると、破壊の時代(例えば戦争、自然災害、社会的危機など)における青年期は、より自律的な範疇になるという事だ。急激な社会的、政治的変化の過程を生きた若者として、SomchitとVilayvanhは、それぞれに違ったやり方でその状況に対処したのである。 成人期に入る寸前に、Somchitの人生は痛ましい個人的出来事に押しつぶされ、威圧的な政治・社会経済環境に捕らわれてしまった。相応の人生を送る可能性の欠如が、彼の移住の決心を支えていたのである。Somchitの境遇は、彼に全てを捨てさせる事を余儀なくした。メコン川を泳いで渡りながら、彼が「携えていたのは自分の身一つであった」(aw tae […]

Memory, mourning, and melancholia figure prominently in the films of Dang Nhat Minh, Vietnam’s national film director and scriptwriter. Born in Hue in 1938, Dang studied in the Soviet Union where he was introduced to […]

Kenangan, kesedihan, dan tokoh melankolis ditonjolkan dalam berbagai film Vietnam. Lahir di Hue pada tahun 1938, Dang belajar di Uni Soviet tempat ia diperkenalkan ke pembuatan film (Cohen, 2001). Hasil kerjanya yang didanai oleh pemerintah […]

ความทรงจำ ความอาลัยและความโศกเศร้าแสดงบทบาทเด่นชัดในภาพยนตร์ของดางเญิตมินห์ (Dang Nhat Minh) ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์ระดับชาติของเวียดนาม เขาเกิดในเมืองเว้เมื่อ ค.ศ. 1938 แล้วไปศึกษาต่อในสหภาพโซเวียต ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทำให้เขาเรียนรู้การสร้างภาพยนตร์ (Cohen, 2001) ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐมีอาทิ When the Tenth Month Comes (1984), Nostalgia for the Countryside (1995), The Girl of the River (1987) และ Don’t Burn (2009) […]

記憶、哀悼、そしてメランコリーは、ベトナムの国民的映画監督で脚本家でもあるダン・ニャット・ミン(Dang Nhat Minh)の映画の中で、一際重要な位置を占めている。1938年にフエに生まれたダンは、ソビエト共和国で学び、そこで映画製作に出会った(Cohen, 2001)。国が出資した彼の作品群、『十月になれば(When the Tenth Month Comes (1984)』、『ニャム(Nostalgia for the Countryside (1995)』、『河の女(The Girl of the River (1987)』そして『きのう、平和の夢を見た(Don’t Burn (2009)』などは、概して国家の共産主義的イデオロギーを宣伝し、戦争の英雄たちを称え、国民の福祉のための集団的な社会闘争を謳ったものである。本稿の焦点となるダンの1999年の作品『グァバの季節』は、この作品群(とその出資者たち)とは相容れぬもので、党路線から外れている(Bradley, 2001: 201-216)。『Mùa ỏ̂i(文字通り、「グァバの季節」)』と題された本作は、ダン自身の短編小説『昔の家』を映画化したものである(Lam 2013: 155)。この作品は、二年がかりのお役所仕事を片付けた後にようやく撮影開始が可能となり、1999年の封切以来、ベトナム国内では上映された事がない(Cohen, 2000)。 『グァバの季節』はフランスで教育を受けたベトナム人弁護士と、彼の親仏的な中流家庭の物語で、背景は1954年から1980年代後期の歴史的大断絶の時代である。弁護士は自ら設計した現代的な屋敷をハノイに建てさせる。物語の中心はこの弁護士の三人の子供たちである。真ん中の子、ホアは、家族が庭に植えたグァバの木の実を採る最中に木から落ちて頭に怪我をする。物語はホアが50歳のところから始まる。彼の一番上の兄のハンはドイツへ移民し、ホアの妹のトゥイが彼の面倒を見ている。現在と過去が静止したままぶつかり合う。頭に怪我をした事によって、ホアの記憶と知能は時間の中に凍結され、1959年から1960年に北部を席巻した土地改革で一家が追い出され、家財を没収された後も没落を拒む(Cohen, 2000)。 筆者の主張は共産主義の神話、共同所有権に対するダンの大胆不敵なカウンター・ナラティブと、個人の記憶の映画的表現が相まって、国家と個人の記憶の間に数多く存在する亀裂を浮彫にしている事である。もう一つの記憶の舞台を設ける事で、『グァバの季節』は個人の記憶の大規模な消去に光を当て、国家の集合的な歴史と記憶の二段階での正当化や、さらにはその「記憶」の背後にある新旧の政治体制にも疑問を投じる。さらには『グァバの季節』が共産主義体制の非情さを拡大してみせるため、中流家庭の家財没収だけでなく、記憶の諒奪の試みによって、等しく腐敗し、矛盾した社会的平等と集団性という共産主義のイデオロギーに余地を作ろうとした事に焦点を合わせる手法も示す。記憶にまつわる政治体制の変化という複雑な物語に対するダンの語り口と視覚表現の想像力に富んだ映画的言語を、三つの主要な局面を通じて分析する。それらは忘却、消去、そして隔絶である。最後に、ダン映画の中で記憶がどのように経験として具現化されるかを示す。 『グァバの季節』は、サンダルを履いた一組の足が、ハノイの現代的な屋敷のフェンスに沿って忍び歩きをする35ミリのクローズアップから始まる(図 1)。このシーンに続くのは屋敷の中から見たフェンスのロングショットである。ホアの顔と目がフェンスの穴から覗き、彼の父親がかつての自宅に植えた一本の背の高いグァバの木を見ようとしている。現在の住人は政府高官と彼の甘やかされた大学生の娘のロアン、そして彼らのために料理や掃除をする年配の女中である。残りの家族は皆、ホーチミン市(サイゴン)にいる。50歳のホアはフェンスをよじ登り、再び自分のグァバの木を訪れようとするのだが、不法侵入で捕まり、警察署へ行くはめとなる。彼の妹のトゥイは、彼を助け出すためにホアが精神障害者であるという確認書に署名をする。 心の痛むようなシーンが繰り広げられ、我々は程なく、ホアが自分の思い出の中に生きている理由を理解する事になる。トゥイは警察署からホアを自転車の後ろに乗せて自宅に連れ帰る。彼女はまるで彼が小さな子供であるかのように服を脱がせるのを手伝い、シャワーを浴びるように言いきかせる。彼の汚れたズボンのポケットの中身を出している時、彼女は彼が父親の植えた木からもいできた一つの緑色のグァバの実を見つける。彼女がそれを手の平に乗せていると、グァバの重みと手触りがトゥイの記憶を呼び覚ます。彼女の家族に何が起きたのか、とりわけ、何がホアの精神を危機的状態に追いやったのか(図2と3)。トゥイはそこで、自分たちの家族の歴史とホアの人生の物語をナレーションで語り、背後には家具がある、彼らの暮らしていた30年前の家の回想シーンの映像が流れる。 『グァバの季節』は、サンダルを履いた一組の足が、ハノイの現代的な屋敷のフェンスに沿って忍び歩きをする35ミリのクローズアップから始まる(図 1)。このシーンに続くのは屋敷の中から見たフェンスのロングショットである。ホアの顔と目がフェンスの穴から覗き、彼の父親がかつての自宅に植えた一本の背の高いグァバの木を見ようとしている。現在の住人は政府高官と彼の甘やかされた大学生の娘のロアン、そして彼らのために料理や掃除をする年配の女中である。残りの家族は皆、ホーチミン市(サイゴン)にいる。50歳のホアはフェンスをよじ登り、再び自分のグァバの木を訪れようとするのだが、不法侵入で捕まり、警察署へ行くはめとなる。彼の妹のトゥイは、彼を助け出すためにホアが精神障害者であるという確認書に署名をする。 心の痛むようなシーンが繰り広げられ、我々は程なく、ホアが自分の思い出の中に生きている理由を理解する事になる。トゥイは警察署からホアを自転車の後ろに乗せて自宅に連れ帰る。彼女はまるで彼が小さな子供であるかのように服を脱がせるのを手伝い、シャワーを浴びるように言いきかせる。彼の汚れたズボンのポケットの中身を出している時、彼女は彼が父親の植えた木からもいできた一つの緑色のグァバの実を見つける。彼女がそれを手の平に乗せていると、グァバの重みと手触りがトゥイの記憶を呼び覚ます。彼女の家族に何が起きたのか、とりわけ、何がホアの精神を危機的状態に追いやったのか(図2と3)。トゥイはそこで、自分たちの家族の歴史とホアの人生の物語をナレーションで語り、背後には家具がある、彼らの暮らしていた30年前の家の回想シーンの映像が流れる。 […]

Commenting on sociologist Maurice Halbwach’s (1925) influential theoretical essay on memory, Paul Connerton declared that continuing to speak of “collective memory” required recognition that the term subsumed “quite simply facts of communication between individuals.” (Connerton […]

Ketika mengomentari esai teoritis berpengaruh karya sosiologis Maurice Halbwachs (1925) tentang memori/ingatan, Paul Connerton menyatakan bahwa untuk melanjutkan membicarakan ingatan kolektif memerlukan pengakuan bahwa istilah tersebut merupakan bagian dari “fakta cukup sederhana tentang komunikasi antar […]

เมื่อความเรียงเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความทรงจำอันโด่งดังของมอริซ อัลบ์วาคส์ (Maurice Halbwachs) นักมานุษยวิทยา ได้รับการตีพิมพ์ออกมานั้น (1925) พอล คอนเนอร์ตัน (Paul Connerton) แสดงความคิดเห็นต่อผลงานชิ้นนี้โดยยืนยันว่า การพูดถึง “ความทรงจำรวมหมู่” (collective memory) ต่อแต่นี้ไปต้องตระหนักว่าคำคำนี้มีความหมายถึง “ข้อเท็จจริงพื้นฐานง่ายๆ เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างปัจเจกบุคคล” (Connerton 2010: 38) ผู้เขียนดำเนินรอยตามบทเรียนขั้นพื้นฐานของอัลบ์วาคส์โดยถือว่า ความทรงจำรวมหมู่ในที่นี้หมายถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่กลุ่มทางสังคมหนึ่งๆ ผลิตขึ้นมา และได้รับการจินตนาการซ้ำและเล่าซ้ำโดยเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบันเสมอ ในบทความนี้ ผู้เขียนใช้ข้อมูลภาคสนามที่วิจัยมานานกว่าเก้าปีในจังหวัดโพธิสัตว์ (Pursat) ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา เพื่อนำมาบรรยายถึงสถานการณ์ที่การสื่อสารของปัจเจกบุคคลได้สร้างและถ่ายทอดความทรงจำรวมหมู่ผ่านสื่อกลางที่เป็นสถานที่ ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็นว่า ความทรงจำรวมหมู่ของชาวเขมรในกัมพูชามีความเชื่อมโยงกับการประจักษ์และการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินอย่างแยกกันไม่ขาด ความเชื่อมโยงนี้สะท้อนถึงความสำคัญอย่างยิ่งของแผ่นดินในหลายแง่มุมของชีวิตทางสังคม นอกจากนี้ […]

社会学者であるモーリス・アルヴァックス(Maurice Halbwach (1925))の記憶にまつわる有力な論文の出版に際し、ポール・コナトン(Paul Connerton)はこれを評して「集合的記憶」を論じ続ける上で、この語には「極単純に、個人間のコミュニケーションの現実」が包含されているとの認識が必要だと言明した(Connerton 2010: 38)。アルヴァックスの根本的な教えに倣い、筆者は本論における集合的記憶の意味を、社会集団によって生み出された過去の出来事のナラティブとし、また常に現状を考慮して再考され、語り直されるものとする。この論文では、9年間に及んだカンボジア西部のポーサット州でのフィールドワークに基づき、集合的記憶を生成し、伝達する個人的活動であるコミュニケーションが、場所を介在して行われている状況を説明する。カンボジアにおけるクメール民族の集合的記憶は、土地に関する認識や慣習と密接に結び付いたものであると考えられる。この結びつきは、社会生活の多くの側面における土地の決定的な重要性を反映するものだ。つまり、集合的記憶は必ずしも国家的なものとは限らず、地域的なものでもあるという事だ。 宗教体系における重要要素としての土地 カンボジアでの土地は、80%の人々が今でも田園地方に暮らす中で生活の中心となっている。また、土地は国民の宗教体系にとっても重要なものである。大地は今なおクメールの宗教体系の中で重要要素であり、その最も明白な例は土地の守護精霊(anak tā)と彼らの住処との深い結びつき(Ang 2000)や、視覚文化に頻繁に引用される大地の女神Braḥ Dharaṇī (Guthrie 2004)である。このような信仰は、古代東南アジアの諸宗教における「大地の力の神格化」という、より大きな概念に支えられたものであり(Mus 1933: 374)、この概念の中で、大地と大地の精霊たち、あるいはヒンドゥ化過程の後にはヒンドゥの神々が融合され、固有の実在となっている。この土地に付された大地の力を神と融合させ得る力は、カンボジアではサンスクリットでデーヴァ・ラージャ(神のような王)信仰として知られるkamrateṅ jagat ta rājyaというアンコール朝の宗教以来、馴染みの深いものとなっている。古典的な解釈では、これを王と(特に)シヴァ神(Coedes 1961)との結合を祝するものと見なすが、別の学者達(Jacques 1985など)は、これがaN anak tāや王の守護精霊の性質の一部を具えた神と見なしている((Estève 2009)。 カンボジアでは、東南アジアの大部分と同様で(Allerton 2013)、そのような信仰が特定の場所にそれ独自の介在者を与える。この介在者はカンボジアでは、主にmcās’ dịk mcās’ ṭī,、「水と大地の支配者」の姿をとって現れる。彼らの主な懸念は、自分たちの土地を不適切な行いをする訪問者や、許しを請わずに木を伐り果物を取る欲深い土地の利用者たちから守る事である。 上の要約はPaul MusやAng Chouleanなどの優れた人類学者達によって詳述されたカンボジアでの土地のオントロジーの基本原理を紹介するものである。筆者は自身のフィールドワークから、カンボジアでは大地と時が異なるオントロジーとしては認識されておらず、むしろ一つの範疇内で括られたものであるとの判断に至った。これを可能にしているのが、クメール人のparamī (boromeyと発音される)の力の認識である。(国あるいは地方レベルで考えられる)カンボジアの領土は、「paramīが充満した」、効験があると認められた場所のネットワークによって構成されている。そのような場所は、特別な古い僧院をはじめ、立派な形をした特定の古木や、樹木が茂り、壊れた像の転がった丘など、様々である。どのような形にせよ、そのような効験あらたかな場所の大半には、宗教や王権にちなんだ歴史上の出来事との関連性が共通して存在している。Judith Bovensiepen (2009)が述べたティモール・レステの事例と同様で、カンボジアの土地は所定の場所で起きた過去の出来事を、いわば「吸収する」事ができるのだ。 上述の大地の性質は、効験のある場所を記憶の場として機能させ得るもので、そのような場所で過去の出来事が記憶され、(とりとめもない事もあるが、大抵は祭祀の根拠についての)解釈を与えられる事で、現代の社会生活や個人生活と関わり合っている。ここで紹介する事例研究の主題は、クレアン・ムアン(Khleang […]

Monuments and statues have long been popular among states seeking to define collective memory. Such obsession with statuary commemoration has even been described by some as a sort of ‘statuemania’, an ailment of national elites […]

Tugu-tugu dan patung-patung telah lama terkenal di kalangan negara-negara yang berusaha untuk menjelaskan kenangan bersama. Obsesi tersebut dengan peringatan patung bahkan telah digambarkan oleh beberapa sebagai semacam ‘patung mania’, sebuah penyakit dari para elit nasional […]

อนุสาวรีย์และรูปปั้นเป็นที่นิยมมานานในรัฐที่พยายามกำหนดนิยามความทรงจำส่วนรวม (collective memory) บางคนถึงกับเรียกความหมกมุ่นที่มีต่อการสร้างอนุสรณ์สถานที่มีรูปปั้นว่า “ลัทธิคลั่งรูปปั้น” (statuemania) ซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตของชนชั้นนำระดับชาติและนักวางผังเมืองไม่เฉพาะในตะวันตกเท่านั้น แต่รวมถึงในหลายสถานที่อย่างประเทศไทยด้วย อนุสาวรีย์ใหม่ๆ เริ่มผุดขึ้นมาเป็นจุดหมายภูมิทัศน์ของเมืองกรุงเทพฯ ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในหลายๆ แง่ ความคลั่งไคล้นี้ยังคงแพร่กระจาย—และขยายตัว—พร้อมกับการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์ที่หัวหิน ซึ่งมีผู้บรรยายว่าเป็น “อุทยานประวัติศาสตร์พร้อมอนุสาวรีย์เจ็ดกษัตริย์ที่รัฐบาลทหารสร้างเพื่อสักการบูชา” ความหลงใหลในอนุสาวรีย์รูปปั้นเป็นสิ่งที่แผ่พ้นปัจจุบัน พ้นศูนย์กลางและพ้นรัฐ ดินแดนเทพนิยายประวัติศาสตร์ราชภักดิ์ของรัฐบาลเผด็จการทหารเป็นแค่การสำแดงครั้งล่าสุดของประวัติศาสตร์อันยาวนานในการสร้างอนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกษัตริย์ในประเทศไทย ในทำนองเดียวกัน โฉมหน้าเมืองที่เปลี่ยนไปของกรุงเทพฯ ในช่วงอัสดงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็เป็นแค่ฉากหลังฉากหนึ่งของลัทธิคลั่งรูปปั้น ยกตัวอย่างเช่น ในจังหวัดภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ไม่เพียงชี้ให้เห็นชั่วขณะสำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองและของภูมิภาคเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันสะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐที่จะยัดเยียดแม่บททางประวัติศาสตร์ฉบับราชาชาตินิยมกระแสหลักครอบทับลงบนความทรงจำของท้องถิ่น ในประการสุดท้าย ลัทธิคลั่งรูปปั้นไม่ใช่แค่ความป่วยไข้ของชนชั้นนำในรัฐเดี่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นอาการร่วมที่แพร่ระบาดในกลุ่มคนกับกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างหลากหลายด้วย เฉกเช่นศิลปินที่แกะสลักปั้นหล่อรูปปั้นมากับมือ ชนชั้นนำระดับชาติและท้องถิ่นก็พยายามปั้นแต่งความทรงจำของมวลชนโดยแสดงออกผ่าน “ความทรงจำที่เคลื่อนย้ายไม่ได้” เช่นกัน ครูบาศรีวิชัย […]
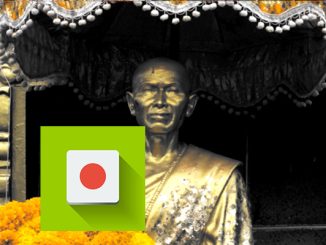
記念建造物や彫像は、集合的記憶の定義を試みる国家の間で久しく普及している。そのような彫像記念物に対する執念は、一部の者たちによって、ある種の「彫像狂」とさえも表現される。これは西洋だけでなく、タイのような場所でも国家のエリートや都市プランナーたちの病なのである。タイでは新たな記念建造物が20世紀初頭からバンコクの都市景観に点在するようになった。この熱狂は様々な方法で拡大を続けており、最近ではタイのホアヒンのラチャパクディ公園の建設が「軍事政権によって安置された7人の王の記念像があるテーマパーク」と表現されている。 この彫像記念物に対する執心は、現在を超え、中央を超え、国家を超えて広がっている。軍事政権のラチャパクディという歴史テーマパークは、王族を記念建造物によって顕彰するタイの長い歴史の最新の現れであるに過ぎない。同様に、絶対君主制の黄昏時におけるバンコクの都市変容は、彫像狂の一背景に過ぎぬものであった。例えば北部都市のチェンマイでは、歴史記念建造物はこの都市及び地方の歴史上の重要期のみを示すばかりか、何よりも、国家が地域の記憶に主流の王党派・国家主義者の歴史テーマを押し付けんとする試みの地域的バリエーションをも示しているのだ。最後に、彫像狂は画一的な国家主体のみが患う病ではなく、むしろ、様々な主体や利害関係によって共有される疾患である。個々の芸術家たちがこれらの彫像を自分たち自身で彫り、鋳造する一方、国家や地方のエリートたちもまた、これらの「不動の記憶」によって表された国民的記憶の形成に取り組んでいるのだ。 クルバ・スリウィチャイ(Khruba Sriwichai) チェンマイに建設された最初期の近代的彫像記念物の一つはクルバ・スリウィチャイ(1878-1938)に捧げられたものである。彼はカリスマ的な僧侶であり、タイ政府の徴兵制度の方針に対する抵抗や、意欲的な寺院再建の経歴、街はずれからドイ・ステープ山頂寺院への道路の建設によって最もよく知られており、これら全てのことのために彼はタイ政府当局側にとって、ちょっとした目の上のこぶとなっていた。 クルバ・スリウィチャイのための記念碑建設を押す動きは、地元から、特にチェンマイ初の議員Luang Sri Prakadによって始められた。記録資料は、彼の記念碑に対する熱意や、政府内でこれを推進し、ドイ・ステープ麓にこれを設置しようとした努力を十分に実証している。一見、このようにタイ政府にとって厄介な人物の記念碑が中央国家によって、これ程強く支持された事を知ると意外に思うかもしれない。この彫像が地方の多様性の認識に向けたより大きな動きの一環だと提言することはあまりにも単純であろう。だが、この記念碑は確かに「地元に、あるいは地域に根差したディスコース」の焦点となったのである。地元のイニシアティブに応じて、タイ政府はこのカリスマ的で厄介な僧侶の遺産を統合せんと試みていたのである。この点において、これは初の試みではなかった。例えば1946年には、タイ王国が援助した公式火葬の後、彼の遺骨は六分割され、北部各県に分配された。1938年に亡くなった時、彼は依然として北部地方のアイデンティティーの象徴であったが、これはタイ政府が牛耳るシャム・タイ国民のアイデンティティーとは、せいぜい異なったものであって、下手をすると正反対のものであった。ようやく18年後の1956年にこの記念碑が設置された時、個人の記憶はなお、この製作と受け入れにとって重要であった。スリウィチャイの記念碑は、彼のカリスマ性の一部を中央国家に移転する事で、この厄介な僧侶の記憶を「手懐け」ようとするものであったかもしれないが、また地元の記憶のディスコースに開かれたままとなっていたのである。 タイ国家はこの記憶の形成を、彫刻家シルパ・ビラスリ(Silpa Bhirasri)の作品を通じて行った。元はイタリアのフィレンツェ出身で、帰化してタイ市民となったシルパは、後に近代タイ美術の父、そしてピブーンソンクラーム首相の主な彫像プロパガンディストと見なされるようになった。Maurizio Peleggiは、ピブーン時代に彫像記念物が「政治的プロパガンダの媒体として配置された」と記している。シルパはバンコクで特筆すべき彫像、例えばタクシン騎馬像の記念建造物などを製作したが、彼がデザインしたバンコクで最も有名な記念建造物は民主記念塔である。彼は他の彫刻家たちも養成したが、その中には彼のスリウィチャイ像の彫刻と鋳造を補佐したKhiem Yimsiriや、チェンマイで最も有名な記念建造物である三人の王の記念碑を27年後に製作する事となったKhaimuk Chutoなどがいる。 三人の王 最も有名で広く複製されるチェンマイの記念碑は中心地に位置し、三人の王族の肖像によって構成されている。それらはパヤー・マンラーイ(Phya Mangrai)、パヤー・ンガムムアン(Phya Ngam Muang)と、通常はラームカムヘーン(Ramkhamhaeng)として知られる13世紀のスコータイ王で、タイ史に慈愛に満ちた王権の概念を打ち立てたパヤー・ルアン(Phya Ruang)である。この記念碑は1296年にこの都市が建設された時、この三人が会ってマンラーイの新たな都市の位置や設計、規模を定め、これが彼の新たなラーンナー王国の首都となったという物語を伝えるものだ。 この記念碑の発端は複雑で、実際にはマンラーイだけの記念碑を建てようとする地元の動きとして始まった。1969年には地方委員会が組織され、マンラーイ記念の取り組みに便宜が図られたが、この委員会が芸術局(FAD)と接触し、この記念碑のデザインを依頼した。彼らはさらにSukit Nimmanhemin教育大臣にも接触し、土地とFADの支持を確保した。1969年の夏にはこの大臣の提案によって、FADはマンラーイの記念碑という概念を、三人の王の記念碑へと変えてしまった。それはなぜか?政府が一年後に行った説明によると、彫像記念物の増殖には「混乱」を招く可能性があったためということで、つまりは、タイ政府によって認可されない歴史の記憶を作り出す事になる、という意味である。1970年3月に政府は新たな政策を発表した。それは、重要人物の記念建造物や記念碑の計画はいかなるものであれ、政府に提出し、政府が検討する必要があるというものだ。地方の彫像狂の問題が、政府の最高レベルの懸念となったのである。それでもなお、一人の王から三人の王への変更問題は、引き続き人々の関心を集めた。6月5日の地元紙は次のように問いかけた。「マンラーイの記念碑:一人の王か三人の王か、どっちが良い?」チェンマイ知事は、他の王たちを入れるとマンラーイの重要性が薄れること、また、特に若い世代向けの説明を追加する必要が出てくるとの不満を述べた。地元の旧チェンマイ王国の子孫たちもまた、マンラーイだけの記念碑の方が良かったようである。 一度、ンガムムアンとラームカムヘーンが加えられると、この記念碑の構成の問題がさらなる論争を生んだ。マンラーイは中央に立っているが、威厳たっぷりに中心となった人物はラームカムヘーンであり、他の者たちは彼の話を聞いているのである。地元民たちの中には、マンラーイを中心から外すというナラティブに不満を表明する者たちもいたが、他の者たちは、なぜラームカムヘーンがもっと中心とならないのかと尋ねた。国家的な見地から見ると、彼は当然、より重要であると考えられるためだ。ラームカムヘーンとマンラーイの主役争いは様々な方法で行われた。例えば、記念碑落成にちなんだ記念のお守りが発行された時、ラームカムヘーンの名前はマンラーイの名前よりも先に、最初に記載されていた。これらの人物のデザインも、また意味ありげである。彫刻家でタイ王妃の親族であるKhaimuk Chutoは、王たちの顔つきを彼らの人柄を反映したものとして思い描いた。マンラーイは美形で、ラームカムヘーンは支配者らしく、ンガムムアンは「ハンサムで気が多い」といった具合だ。 おそらくタイ政府の観点から見れば、マンラーイとラームカムヘーンを二つの中心とする事は妥協であっただろう。だが、チェンマイの観点から見ると、これは国家の歴史を地方の記憶の上に押し付ける事であった。一人の王の姿を三人に増やす事で、この記念碑は歴史的ディスコースをタイ国家の指示通りに再び中央化し、チェンマイの歴史をバンコクの歴史と結びつける事となったのだ。 彫像が体現するもの これらの彫像は世俗的な記念建造物として存在するだけでなく、信仰や儀礼の対象でもある。事実、世俗彫像と宗教彫像との境界線は、大部分の東南アジアにおいては不明瞭である。バンコクの王たちやその他の人物の彫像記念物は、容易に崇拝や儀礼の中心となり得るものであり、多くの本物そっくりの僧侶の彫像が地域の博物館や寺院に設置されている。完成した後の三人の王の彫像がチェンマイに入る様子は、古代の王たちさながらで、市内北部のチャンプアック門を通った後に市内中央の聖域に進んで行った。彫像はまるでそれらが王たちであるかのように動かされ、今日では代々の王権を体現するものとしてあがめられている。この記念碑はタイ政府による支配をよそに、市内中心部の呪力・霊験を主張する競合集団によって再解釈され続けている。 同様に、クルバ・スリウィチャイ記念碑もまた、宗教的、世俗的、両方の記憶を体現している。例えば1972年には、スリウィチャイとその弟子が山麓に建設した道路の基点近くに位置するWat Sri Sodaという寺院が、この彫像の寺院敷地内への移動を要求した。実際、彼らはこの彫像を宗教的彫像として要求し、彼らの方がこの彫像をより良く保護する事が可能であり、功徳を積むための儀式にも便宜が良くなると主張したのである。地元Khon Muang紙に発表された論説はこの計画に強く反論し、それをただの金儲けとして、元々の場所が選ばれたのは、この彫像を広い範囲から見えるようにするためであり、それによって人々がこの高僧の善行を記憶しておく(ramlukthung)役に立つからであると主張した。現在、この記念建造物は元の位置に留まり、記憶と崇拝の焦点となっている。 結論 全ての記念建造物は集合的記憶を幾分、歪めるものである。上で検討した記念碑は、今日のチェンマイに数多くある、歴史的記憶が姿形を与えられた場所のうち、ほんの二つの場所である。三人の王、あるいはクルバ・スリウィチャイ記念碑移動の簡易計画をめぐる論争は忘れられるべきではない。なお、一度は議論の的となった彫像を、地域のアイデンティティーの象徴として再配置する事も可能である。三人の王たちのシルエットを用いて、何でも北部、ラーンナー、あるいはチェンマイの標識とする事ができる。ニューヨークに自由の女神があるのなら、チェンマイには三人の王があるのだ。芸術家たちがこれらの彫像を刻むのと同様に、社会的、政治的諸勢力は記憶の風景を形成する。だが、「彫像狂」を地域的観点から検討することで明らかとなるのは、地域の記憶を体現するものに対する細かい政治的制限が、どのようにラチャパクディ公園にあるような彫像、つまりは、軍部の認めた超王党派、超国家主義者版タイ人のアイデンティティーと歴史のぶしつけな道具を作り出すことができるのかという点である。 Taylor M. Easum […]
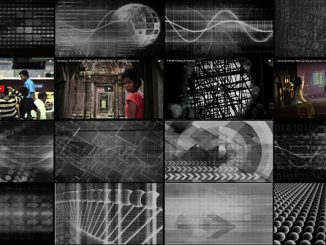
Central to the Thai term for memory khwamsongcham = ความทรงจำ is song, which literally translates as form or medium. The word khwamsongcham in itself forges an embodiment of the past (albeit always interpreted), and signals […]
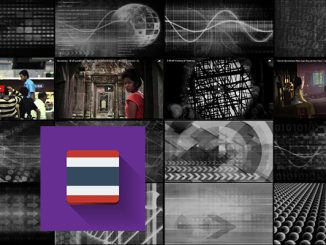
ในภาษาไทย คำว่า ความทรงจำ คำที่อยู่ตรงกลางคือคำว่า ทรง ซึ่งแปลตรงตัวหมายถึงรูปทรงหรือสื่อกลาง คำว่า ความทรงจำ ในตัวมันเองจึงหล่อหลอมความมีตัวตนของอดีต (ถึงแม้ผ่านการตีความเสมอก็ตาม) และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงศักยภาพที่จะแปรเปลี่ยนความทรงจำผ่านรูปทรงและสื่อกลางต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติในสังคมและวัฒนธรรมวัตถุด้วย คนเราทุ่มเทให้การสร้างตัวตนแก่ความทรงจำก็เพราะกลัวว่าจะลืม ประเทศไทยผ่านการรัฐประหารโดยกองทัพมาแล้ว 12 ครั้งนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน พ.ศ. 2475 การที่กองทัพหวนกลับมาปกครองประเทศครั้งนี้ ทำให้เกิดประสบการณ์แบบย้อนอดีต (déjà-vu) ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่จุดชนวนให้เกิดแรงต่อต้านในวงสังคมกระฎุมพีชาวกรุงเทพฯ เรากลับเห็นแต่การตอกย้ำเรื่องเล่าแม่บทที่ล้นเกินด้วยแนวคิดความมั่นคงของชาติและการรักษาความเป็นระเบียบของสังคม “กลิ่นอาย” ของเผด็จการอำนาจนิยมแบบกองทัพสร้างความรู้สึกคุ้นเคยถึงขนาดที่การรัฐประหารของกองทัพทำให้เกิดการเฉลิมฉลองในปี 2549 และยอมรับได้ในปี 2557 ในหมู่กระฎุมพีเสียงข้างน้อย—หรือมิใช่? ในขณะที่ข่าวพาดหัวของสื่อกระแสหลักอาจบอกเป็นนัยๆ ว่า คนไทยยอมรับการปกครองของกองทัพและการธำรงสถานภาพเดิมไว้ แต่เราขอแย้งว่า ภาพยนตร์อิสระทำหน้าที่สวนกระแสโดยนำเสนอเสียงคัดค้านผ่านความคลุมเครือทางการเมือง วัฒนธรรมของพื้นที่สาธารณะทางเลือกในภาพยนตร์ไทย […]
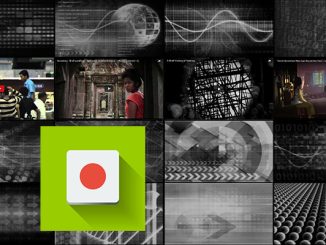
タイ語の記憶にあたる言葉、khwamsongcham = ความทรงจำの中心はsongであり、これは文字通り形式、あるいは媒体と訳される。khwamsongchamという語は、それ自体の中に具体的な(常に解釈されたものではあるが)過去を作り出し、社会的慣習や物質的文化などを含んだ様々な形式や媒体を通じた記憶の変容能力を示唆している。人が具体的な記憶に努めるのは、忘却への恐れがあるためだ。タイが12回連続で軍事クーデターを経験したのは、絶対君主制から移行した1932年以降の事である。今回の軍事政権の出現は既視体験を呼び起こしたものの、残念な事にバンコク中産階級の公共圏に抵抗運動を引き起こす事はなかった。そこに見られるものは、国家安全保障や社会的秩序の維持などに溢れたグランド・ナラティブの強化である。この軍事独裁主義の「感じと匂い」は、軍事クーデターが2006年に讃えられ、2014年には中産階級の少数派から許容可能なものとして容認され得るよう、親近感を作り出した(のであろうか?)。主流メディアの報道は、タイの人々が軍事政権と現状を受け入れているかのように仄めかすであろうが、我々が論じる自主映画は、対抗的公共圏として機能し、巧みな多義的表現を通じた抵抗を提供する。 タイ映画における対抗的公共圏の文化 現代のタイにおける独裁主義的状況の中、報道機関やオンラインのソーシャルネットワーク、ウェブ2.0の公共圏は縮小してしまった。ところが、ミクロの対抗的公共空間や反体制的社会運動は増えている。道徳的秩序が国家安全保障と混同されるようになり、この秩序を乱すと思しき思想や表現の罪には法廷での訴訟や罰金、パスポートの取り消し、国外追放、実刑判決などによる処罰が可能となった。国家検閲の強化は反対意見を抑圧するよりもむしろ、新たな政治色の強い自主製作のタイ映画を生み出すこととなった。製作やキュレーターシップにおける新技術、またソーシャルメディアを通じた新たな配給回路などがこれを可能にしたのである。 マイケル・ワーナー(Michael Warner)が示唆するように、「オルタナティブな公共圏が社会運動として位置づけられる場合、それらは国家に対する働きかけとなる。それらは政治の一時性に加わり、自身を合理的で批判的な言説の遂行文(performatives)に適応させる。多くの対抗的公共空間にとっては、そうすることは政策のみならず公共生活空間そのものをも変化させようとしたもともとの願いからの譲歩となっている。」タイの有識者や映画製作者たちが、彼らの反対意見を私圏に止めておくことを拒否することが、ミクロ・オルタナティブ・アート・スペース(カフェやギャラリー)の出現や、YouTubeやウェブ2.0などへのオープン・アクセスでのオンライン参加をもたらすことになった。これらの新たなミクロ対抗的公共空間は、多義的な風刺や両義的な語句を用いることで逮捕を回避している。 タイ(当時はシャム)映画の最初の国家検閲は1930年の映画法令であった。過去10年の間に新たな検閲法が出現し、刑法(1956, 2007)112条のコンピューター関連犯罪法(2007)と国内治安法(2008)の改正によって不敬罪法が拡大された。同じ10年間に、20作以上の自主映画が製作され、国内外の主要映画祭で公開上映されてきた。タイでインディーズ映画の拠り所となっているのは都市部のカフェや本屋、ギャラリー、領事館、それに大学などの場である。映画評論家のKong Rithdeeによると、タイ映画財団は「短編や自主映画を製作するタイの映画作家たちのための公共圏の創出にとりわけ重要な役割を果たし...映画およびデジタル映画の民主化」を、ワークショップや番組制作、映画祭などを通じて行っている。このような形で、インディーズ映画は政治的暴力の再考と記憶のための領域を切り開いてきたのである。 対抗的公共空間としての自主映画が細心の注意を払ってきたのは、記憶・歴史、そしてスローな映画美学であった。以下に論じる諸作品は、これら全ての特質を備えたものである。ここで取り上げる作品は、タイで繰り返される政治的暴力との対話、公開上映の機会が一回以上のものであること、また作品がオープンソースの中道左派のオンライン・ニュース・メディア、たとえばprachataiなどで再流通しているものであることを選択基準としている。 実験的ドキュメンタリーは記憶する:テロリスト(2011) タンスカ・パンジッティヴォラクル(Thunska Pansittivorakul)の映画「テロリスト(Terrorist)」は対照的なプラットフォームを備え、国家の政治的暴力の様々なシーンが親密な家族の記憶と並行して再現される。この映画は作品それ自体として見つけることが難しく、DVDやVCDの市場に流通もしていなければ、YouTubeなどのプラットフォームでその全編を入手できるものでもない。予告編は明らかに衝撃的で、男性のマターベーションのシーンが最近の2010年のバンコク路上の政治的暴力のシーンと並置される。この鑑賞体験は、同時に起こる性的、肉体的な暴力と喜びを直感的に具現化したものである。オンラインのニュースソースprachataiの抜粋では、ヌードシーンを避けて、政治的暴力のシーンのみが表示されている。 [youtube id=”bxwS3WN1NTA” align=”center” maxwidth=”800″] 映画の特別な見どころは、タンスカの母親がタイ共産党に加わった経緯についてのオーラル・ヒストリーを、母親と一緒にいる子供のタンスカの写真や、1976年10月6日の虐殺の写真と並置していることである。写真は我々の最も私的な記憶についてさえ、その証左として残す。写真はまた、1976年10月の虐殺の残虐性と衝撃的要素の紛うこと無き証言を提供する事もできるのだ。その残虐行為を暴力シーンの再現によって記録するにあたり、写真はまた、殺された者たちと暴力の関係者であった「国家主義的市民や国家当局」の両者を非人間化させる事も可能なのだ。 「空低く大地高し(バウンダリー タイの主要な劇場で商業上映され、Vimeoで18+の評価を受けた「空低く大地高し(2013)」は、南部の弾圧-2008年プレアヴィヒアにおけるタイ・カンボジア間の銃撃戦-に加わるよう召集され、その後、2010年5月に赤シャツ隊の鎮圧に送られた一人の若者の生涯を追う。この映画の原題“Fatum Paendin Soong”「空低く大地高し」が物議をかもしたのは、これがタイの社会的不公正や社会的階層化に異議を唱えるものと思われたためであった。タイ語での境界は“khet daen”として周知されている。ノンタワット・ナムベンジャポン(Nontawat Numbenchapol)監督によると、「境界の一つ目の意味は、貧しい農村の人々と搾取的なバンコクの中産階級とを分けるものである。二つ目の境界は、カンボジアの人々を国境によってタイから隔てるものである...私はプレアヴィヒアの山の国境に立っていた事を思い出した。その場所で、空と大地がつながり、共に存在していると感じていたのです。そのメタファーは、タイがいつの日か和睦する事を願ったものでありました。」要するに、この映画が具現化しているものは、国家がつくり出す領土や境界を通じた、現在にとっての過去、あるいは過去にとっての現在である。 [youtube id=”ONvbctIqjso” align=”center” maxwidth=”800″] ディレクターズ・カットでは、バンコクのラチャプラソン交差点での王の83歳の誕生日祝いのシーンが、ほんの数か月前に同じ場所で起きた赤シャツ隊の虐殺のシーンに入れ替わり、王族の賛辞や歓声、祝祭と共に映し出される。この並置は、場所が持つ複数の意味あいについて内省を促し、祝祭がどのように虐殺という汚点を置き換え得るかという設問を提起する。この多義的な表現ゆえに、タイの検閲委員会はこのシーンの削除を要求し、監督はこれに応じることとなった。2007年の112条の導入以来、国家当局は君主制に関するあらゆる発言の監視を余念なく集中的に行うようになり、不敬罪の違反者たちを政府の脅威である危険人物として標的にしている。 同様に、複雑な過去から構築されたタイ・カンボジア国境は、国内の政治問題を通じた敵の国家的記憶を具現化したものである。Pavin Chachavalpongpun、Charnvit Kasetsiri、Pou Suthirakの研究が示唆するように、タイ・カンボジアの国境は、歴史、記憶、政治や経済関係によって構築されている。境界はここでは字義通りの意味では用いられず、むしろ過激な国家主義や国内の政治問題の温度によって決められる敵か味方かの要素の狭間の動きを示している。 「ブリーフ・ヒストリー・オブ・メモリー(A […]
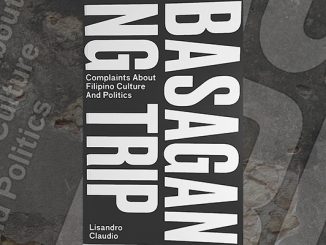
Basagan ng Trip makes theorizing and “discourse” chic. In the Preface, Lisandro E. Claudio notes that “Walang basagan ng trip” mirrors an “anti-critic tradition in Philippine arts” (p. ix). Through this lens, the Filipino psyche encourages creation and discourages criticism as this ruins the vibe of the imaginative process that produces something new. […]

Mata Hati Kita, The Eyes of Our HeartsCompiled by: Angela M. Kuga Thas and Jac SM Kee Petaling Jaya: Gerakbudaya Enterprise, 2016, 142 pages The recent widespread impression that religion, especially Islam, is to blame […]
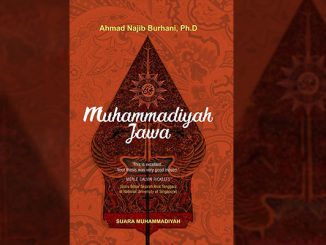
Muhammadiyah JawaAuthor: Ahmad Najib BurhaniYogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016. 184 pages A Muslim organization in Javanese culture Muhammadiyah Jawa is an important work written on historical development of Muhammadiyah, an Islamic organization established in 1912. […]

从文化视角看大湄公河次区域合作《评大湄公河次区域五国文化发展的体制机制研究》 (Viewing GMS Economic Cooperation from Cultural Horizon: Review on Study on Mechanism of Cultural Development of 5 Countries in the Greater Mekong Sub-region) 王士录 (Shilu Wang) Publisher: Yunnan Publishing Group and Yunnan People’s Publishing […]
Copyright © 2024 | Kyoto Review of Southeast Asia | All Rights Reserved