
東南アジアにおける君主制
東南アジア研究の重鎮、故Michael Leifer教授は、Roger Kershawの絶賛を受けた “Monarchy in Southeast Asia”というタイトルの本に序文を書いた。Leiferは次のように述べた。「世間一般に、君主制が不合理な存在になったというのが通念である。東南アジアの場合、この原理が通用するのはある程度までの事だ。植民地主義によってもたらされた制度の激変や廃絶をよそに、この地域には一つの支配権を伴う君主国(ブルネイ)と、3種の立憲君主国(カンボジア、マレーシア、タイ)が存在し、それらには相当な政治的重要性がある」。 1 Kershaw自身、Leiferの発言に対して、ある興味深い疑問を提起している。それは次のようなものである。「君主制の存続という不合理は、伝統的政治価値が根強いため、その自然作用によって生じるのか、あるいは、その存在はある程度偶然であったとしても、今やエリート(君主たち自らさえ)によって操られているのだろうか。そのようにして、彼らは近代化の破壊的で安定を損ねる影響に先手を打とうとしているのか・・・その近代化こそが君主制の存続を、むしろ予測のつかぬものにしているように思われる」。 2
この小論文は上記のコンテキストに由来するものである。だが、先行研究で行われたように、この主題を不合理と論じる代わり、本論では新たな政治情勢下での東南アジアの君主制の存続について、いくつかの指針を提示する。
Kershawは、近代化を君主制に対する脅威と論じた点で正しかった。実際には、近代化のみが君主制の政治的妥当性に挑んだのではなく、民主化もまた、その存在を脅かすものであった。過去10年間、民主化の波は東南アジアを席巻し続けてきた。長年のインドネシアの独裁主義がついに終焉を迎えたのも、この国が民主化という新時代に向かって歩みを進めたためであった。1962年以降、世界から孤立し、以前はビルマという名であったミャンマーは、目下新たな政治改革を迎えようとしている。世界各地、特に中東では、民主主義が大いに必要とされる価値観となった。この風潮の中で東南アジアの君主制は、より厳密な監視のもとに置かれる事となった。君主制が残る国々では、より多くの人々が核心的な疑問を問いはじめた。それは君主制が民主主義と両立するのかという疑問である。
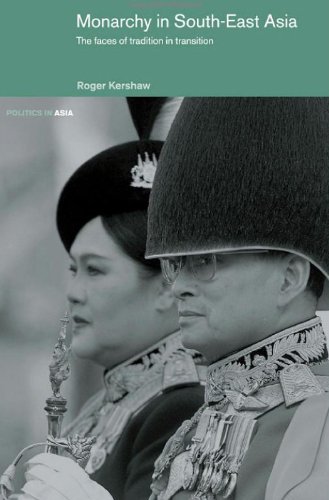
2008年には、ネパールが絶対君主制を廃止、ネパール連邦民主共和国の設立を宣言した。239年間続いたネパールのシャー王朝の終焉は、君主制が民主主義に拮抗する様であれば、これが極めて脆弱になる事を示した。王家も含み、様々な政治的アクターの間には現代ネパールにおける君主の適切な役割について、根本的な考えの違いがあった。ネパール王室が政治に積極的な役割を果たす事を主張し、自らを再び「国家」の中核と位置付けた事に対し、政治家たちは、王室の役割を憲法に示された通りのものとしか捉えていなかったのだ。換言すれば、国王は君臨すれど統治せず、という事である。 3 ある程度、国王の政治介入がネパールにおける絶対君主制の崩壊を招いたのである。
東南アジアには、民主化の波から自らの統治を上手く守り抜いた王室もある。中には廃絶の標的となる可能性がある君主国も存在する。現時点では、東南アジア10カ国中、4カ国が、さまざまな種類の君主制を維持しているが、それらは絶対君主制や立憲君主制、儀礼的君主制などである。今回の特集では、タイ、カンボジア、マレーシア、そしてブルネイにおける君主制について、その将来の展望が論じられる。
プーミポン・アドゥンラヤデート国王は、世界で最も長く在位している君主であり、タイ政体の中枢である。彼が即位したのは1946年で、これは彼の兄、アーナンダ・マヒドン国王の謎の暗殺を受けた即位であった。ブルネイのスルタン・ハサナル・ボルキアは、民主的な国民国家の時代に自らの絶対統治の正当性を掲げ、その耐久力を示した。カンボジアのシハモニ国王の役割の多くは儀礼的であるが、それはクメール民族の国家アイデンティティの構築に重要な役割を果たすものである。しかし、この王室の立場は、人気の高かったノロドム・シアヌーク前国王が2012年10月に死去した後、おぼつかないものとなってしまった。マレーシアには選挙に基づく君主制のシステムがある。ヤン・ディ・ペルトゥアン・アゴンはマレーシアの憲法によって創設された最高官位である。現在の第14代ヤン・ディ・ペルトゥアン・アゴンは、スルタン・アブドゥル・ハリムであり、彼はクダ州のスルタンである。彼の治世は2011年12月13日に、彼が統治者会議に選出されてから始まった。
西洋では、民主的な政府機構が普及する中、君主制は政治の遺物と見なされるようになった。英国王室が存続した事は、この王家が国内の政治的展開に遅れをとらぬよう、絶えず自らの再構築を行ったためである。Dennis Kavanaghは次のように述べた。「英国における君主制存続の鍵は、過去3世紀の間、彼らが君主制廃絶の要求をかわすべき機運に、その権限の譲歩に意欲的であった事だ」。 4 東南アジアでは、王やスルタンたちの統べる、過ぎし時代の面影が、民主主義の時代の中を生き延びてきた。だが、これはいつまで続くだろう。
長期に及んだタイの政治危機では、対立派閥が熾烈に争った。この争いは結局のところ、彼らの権力情勢を強化するためのものであったが、これは偉大な国王を、さらなる政治的深淵に深く引きずり込んだ。だが、公正を期するために言うと、プーミポン国王は常に力を具えた国王である。 5 また、2006年の軍事クーデター以降、タイ王室の一部のメンバーは、もはや舞台裏で策を弄し、私利を図るような真似はやめ、自ら脚光の中に歩み出たのである。例えば、シリキット王妃が王室支持者である民主市民連合の「黄色いシャツ」の一員の葬儀に参列した事は、確実に王室の政治干渉と認識された。彼女が葬儀へ姿を見せた事は、「赤いシャツ」の連中を激怒させた。
ブルネイのスルタンはこれまでのところ、その手腕を発揮して、国内の政治体制が新たな問題に対応し得るよう調整してきた。彼は自身の正当性を強化するため、“Melayu Islam Beraja (MIB)”(「マレー主義に基づくイスラーム的王政」)のイデオロギーを用いるが、これはイスラーム文化の重要な役割を、国家レベルで認めるものである。だが、このプロセスは排他的なので、国内の非ムスリム人口によって受け入れられない恐れがある。
一方、その他の王族たちは、醜聞や不正行為にまみれてきた。これらが王族のイメージを傷つけ、その存続の脅威として浮上してきたのだ。例えば、トゥンク・テメンゴン・モハマド・ファクリーは、マレーシア、クランタン州の王子であるが、彼は17歳の元モデルの妻を性的奴隷のように扱った事で起訴された。マレーシア王家の多くのメンバーをめぐる問題は、これに始まった事ではない。Hazliza Ishakは26歳の元モデルであり、マレーシア、ペラ州の王位継承順位第二位にあたるRaja Jaafar Raja Muda Musaの第二夫人であった。2002年には、イポー付近で彼女が死亡しているのが見つかった。彼女の死は本格的な王室スキャンダルに火を点け、これは数か月の間、国民たちの関心を離さなかったのである。
インド人の学者Sreeram Chauliaは、アジアの君主制の将来が、君主たち個人の能力とその政治手腕の配剤、そして、彼らが民主主義にとっていかに非脅威的要素であるかを周知させられるか否かにかかっていると論じる。 6 同様に東南アジアのコンテキストで、君主制の存続を大きく左右するものは、君主たちの3つのレベルにおける自己改革能力である。そのレベルとは、個人、国家、国家間である。
個人的レベルで、君主たちはこれまで以上に自身のさらなる説明責任や透明性、そして責務を示す必要がある。民主的政権との共存を望むのであれば、そうする事が必要である。東南アジア大陸では、王権神授の概念に対する崇拝の念が依然と強い。タイやカンボジアの王たちは、仏教のダンマラージャ、あるいは有徳の王として、その務めを果たすとされ、彼らはそのようにしてカリスマ性を高め、ひいては目下の者たちからの敬意を集めるのである。これとほぼ同様に、スルタン達もまた、イスラームに基づいて王権を行使する事を示さなくてはならない。王権の宗教的尊厳は、君主制の存在にとって不可欠である。この事は、王権と宗教との密接な結びつきを示す。そして、これが賢明に利用されれば、君主たちの神性のレベルを強化する事も可能である。ネパールの絶対王政が、ギャネンドラ・ビクラム・デーヴ国王の統治下に廃止となった事は、彼が宗教的カリスマに欠けていた事にも多少由来する。Chauliaは次のように述べている。神を祖とする神話は、常に王権の基盤となってきた。しかし、この事は同様に、神聖なる王は公正で非の打ちどころの無い潔白を以て君臨すべきであるという大衆の期待をも暗示する。カリスマ性は、たとえそれが宗教的な血族世襲の継承者であっても自然に生じるものではなく、人々に王権の宗教的尊厳を想起させるような行為を通じて獲得される。ネパールのギャネンドラは、この重要な側面を忘れ、彼の前任者が築いた尊敬や崇拝の念を、残りの限り使い果たしてしまった。個人的な放逸から犯罪行為の疑惑まで、ギャネンドラが封じ込める事のできなかった王族の醜聞や悪評が、大衆の面前で彼の墓穴を掘ったのである。 7
国家的レベルで、君主制の耐久力と複雑に関わっているのが、軍部との協調関係である。歴史を見ればわかるように、軍部は常に王室機関の擁護者であった。君主たちは昔も今も、軍部との間に親密な協調関係を築こうとしてきた。それは、「王室」という前置きの付いた国家軍が、一部の国に存在する事からも察せられよう。タイ国軍がタイ王国軍となった事は、王が最高司令官であることを暗示している。タイの場合、プーミポン国王は、明らかに軍部の確固たる支援を大いに享受している。プレーム・ティンスラーノン陸軍大将は枢密院議長で、元首相(1980-88)であるが、この地位は国王自らにより任命されたものである。ある時、彼は次のように述べた。「軍は王に使える馬であり、政治家ではない」。 8 事実、軍部には強力な権能があり、しばしばこれが君主政治、専制政治、そして民主主義政治まで、あらゆる類の政権の存続期間を決めるのである。君主制長期存続の要は軍部の忠誠である。しかし、国王と軍部の親密な関係は、決して王権の安定を保証するものではない。このような結びつきが、民主主義を脅かすような場合は特にそうだ。改めて、現在のタイにおける危機が示している事は、王室と軍部の協調関係が今や、徐々にその力を失いつつあるという事なのだ。赤いシャツ運動は、政治の軍部支配に立ち向かう決意をしたのである。また、王室が政治に関与する事により、いわゆる反王政分子がタイに誕生する事となった。
最後に国家間レベルで、王室は彼らの存在が強力な海外の同盟国との関係に利するものである事、また、君主制が絶対不可欠な政治制度であり続ける事を確実とせねばならない。外国勢力の支援は、危機の際、特に政治的敵対勢力を撃退する際の方便となり得る。アメリカ合衆国は、この地域に共産党の脅威が広がっていた時期、タイ王室の安全を保障する存在と認識されていた。
これら、東南アジアにおける君主制の長期存続のための指針は全て、自然とバラ色の未来図をもたらすものではない。時折、新たな要素が生じ、彼らの統治の完全性や正当性を試す事となる。不当な対抗手段でこれらの試練に立ち向かうなら、それは逆効果となるだろう。不敬罪法が反王政分子に適用された事により、タイの人権事情をめぐる重大な懸念が生じている。より厳しい手段が君主たちの絶対権力を示すとは限らない。むしろそれは、彼らがその権力に必死でしがみつかんとする姿を示すのだ。
君主制は何千年もの歴史を持つものである。その力は以前より弱まり、中には消滅した例もある。世界中の国民達が、当然、程度や形式は様々であっても、民主主義を政府の最終形態と認めてきたためである。したがって、君主制存続のための究極の鍵は、国民たちの民主主義に対する高まる要求に対し、君主制がこれを補うように働きかけ、あるいは応じる道にかかっているのだ。
Pavin Chachavalpongpun
京都大学東南アジア研究所
References
Chaulia, Sreeram. 2008. Monarchies in Asia: Crowns Die Hard. Opinion Asia, 11 June <sreeramchaulia.net/publications/Monarchies%20in%20Asia.doc> (accessed 27 December 2012).
Joshi, Bhuwan L. and Rose, Leo E. 1966. Democratic Innovations in Nepal: A Case Study of Political Acculturation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Kershaw, Roger. 2001. Monarchy in Southeast Asia: The Faces of Tradition in Transition. London: Routledge.
Magone, José M. 2011. Contemporary European Politics: A Comparative Introduction. Oxon: Routledge, 2011.
Thongchai, Winichakul. 2013. The Monarchy and Anti-Monarchy: Two Elephants in the Room of Thai Politics and the State of Denial. In ‘Good Coup’ Gone Bad: Thailand’s Political Developments since Thaksin’s Downfall, edited by Pavin Chachavalpongpun. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Notes:
- Roger Kershaw, Monarchy in Southeast Asia: The Faces of Tradition in Transition (London: Routledge, 2001), p. XI. ↩
- Ibid, p. 6. ↩
- See, Bhuwan L. Joshi and Leo E. Rose, Democratic Innovations in Nepal: A Case Study of Political Acculturation (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), pp. 386-7. ↩
- Quoted in José M. Magone, Contemporary European Politics: A Comparative Introduction (Oxon: Routledge, 2011), p. 176. ↩
- See, Thongchai Winichakul, “The Monarchy and Anti-Monarchy: Two Elephants in the Room of Thai Politics and the State of Denial”, in ‘Good Coup’ Gone Bad: Thailand’s Political Developments since Thaksin’s Downfall, edited by Pavin Chachavalpongpun, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013). ↩
- Sreeram Chaulia, “Monarchies in Asia: Crowns Die Hard”, Opinion Asia, 11 June 2008 <sreeramchaulia.net/publications/Monarchies%20in%20Asia.doc> (accessed 27 December 2012). ↩
- Ibid. ↩
- In his interview with Far Eastern Economic Review, see <http://testfeer.wsj-asia.com/free-interviews/2006/september/general-prem-tinsulanonda1> (accessed 27 December 2012). ↩
