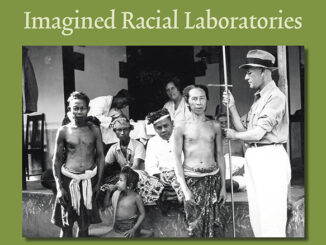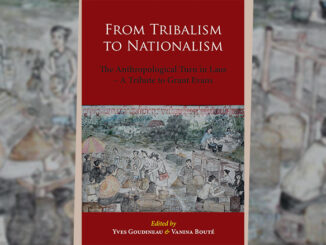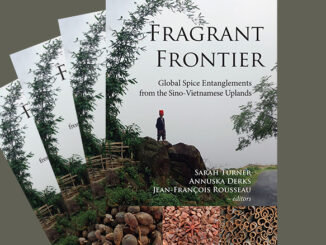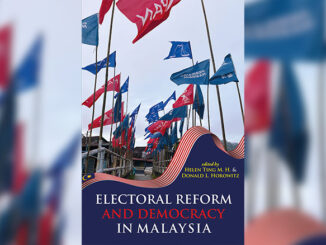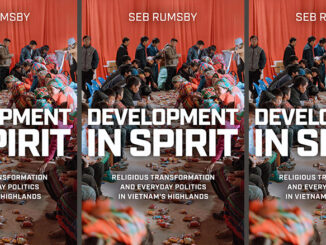この記事では、コロナ禍などの危機が、いかにインドネシアの労働者搾取を強化する仕組みとして利用されたか、また、組合指導者や労働運動家が、これらの現象に対する国内の労働運動をどう捉えているかを論じる。 国民に不利な法律 この記事を執筆する2025年3月の末、インドネシアの多くの都市の路上は、何日も、学生や労働者、一般市民からなる大勢の抗議者であふれている。彼らの要求は、2025年3月20日に下院で可決されたインドネシア国軍法(the Indonesian Military (TNI) Law)の撤廃だ。旧法を改正した新法が問題視されるのは、これが文民統制(civilian supremacy)に反するためだ。特に、そのいくつかの条項は、「民政と軍政の境界を曖昧にしかねず」、疑問の余地があり、独裁的な新秩序時代を連想させ、これを復活させる可能性がある(Paat & Rivana, 2025; Saputra, 2025; Tempo, 2025)。また、この法改正のプロセスも性急なもので、「国民の参加、または、有意義な参加の機会がほとんど」与えられなかった(Saputra, 2025)。だが、批評家によると、このような透明性の欠如は、下院での法案の審議と作成には「ありがちな問題」だ(Tempo, 2025)。 実際、これは新型コロナのパンデミック中に、市民に広まった反対も顧みず、2020年10月5日に下院で可決された「雇用創出に関するオムニバス法(Omnibus Law on Job Creation / Undang-Undang Cipta Kerja)」を彷彿とさせる。当然、これも同法の撤回を求める全国的な反対運動を引き起こした(Prasetyo, 2020; Lane, 2020)。この法案が可決される前、市民団体は「全てのインドネシア国民の人権を尊重、支持、保護する観点から」同法案の審議を中断するべきだと主張したが、審議は「秘密裏に」進められた(Panimbang, 2020)。 このオムニバス法の恩恵を受けたのは資本家階級と、その取り巻き連中だけだ。これは労働法や、鉱業規制、環境保護などの分野に関する約79の現行法を改正する法律だ。そして、この法改正の目的は、労働搾取や土地収用などの常套手段を使い、海外から投資を呼び込むことにあった。ここでは、「雇用の創出」という語が使われるが、それが「どのような雇用か」という問いの方が重要なのは言うまでもない。要するに、ここでは「雇用の創出」と言いながら、インドネシア国民、特に労働者の福利と、環境が犠牲になっている。 労働問題だけについても、この法律は「雇用を創出する」どころか、労働のフレキシブル化(labor flexibilization)を促し、安定した雇用を脅かした。その結果、公共財と公共サービスが民営化され、病気休暇手当や退職手当などの労働者の様々な権利が侵害され、最低賃金や、その他の面にも影響を及ぼす(インフレなどの)いくつかの重要な基準が削除された(see Panimbang, 2020; Izzati, […]