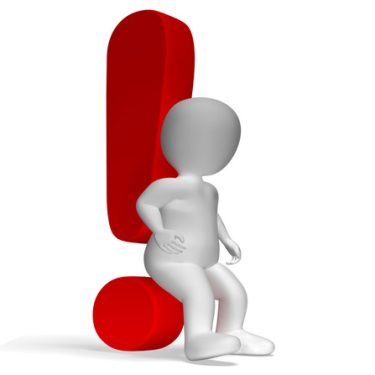元米国防長官のドナルド・ラムズフェルド氏は、2002年2月12日に意味論史に残る人物となった。この時、彼はイラクにおける “Known Knowns (既知の知)”、 “Known Unknowns (既知の未知)”と“Unknown Unknowns (未知の未知)”に関する非常に複雑な説明を行った。私はどちらかというと彼と同意見で、これが複雑な問題の分析にとって便利な概念的枠組であると考える。実際、NASAはこれを用いて宇宙ミッションを計画し、既知の知、既知の未知、未知の未知によるリスクに対処する準備を整えてきたのである。彼の秀逸なアプローチを用いて、南シナ海論争の複雑性に光を投じてみよう。
既知の知
既知の知は我々が知っているという事を知っている事であり、我々が周知している知識である。2013年には南シナ海で比較的穏やかな状況が観察された。ASEANと中国は、2013年に戦略的パートナーシップの10周年記念を祝った。この晴れやかな機に、中国は南シナ海における節度をいくらか示す事となった。これと同時期、ASEANは日本との対話パートナーシップの40周年も祝っている。一年に及ぶ祝典が最高潮に達したのは、12月13日と14日に行われた第二回 日・ASEAN特別首脳会議であった。日本の安倍晋三総理大臣は、ASEANが日本の新たな安保上の積極的役割を支持する事を望んでいた。しかし、東京の特別首脳会談で、ASEANの首脳陣と会合した際、彼がそのような支持を得る事は全くなかった。大多数のASEAN首脳たちは、非常に用心深い様子で、日本が少しずつ新たな安保上の積極的役割を構築し、東北アジアの近隣諸国、特に中国や北朝鮮を警戒させるような事がないよう望んでいたのである。
それにもかかわらず、安倍政権は「積極的平和主義」という新たな戦略計画を進めつつあり、それには軍事費の増加やアメリカとのより緊密な軍事同盟、ASEAN諸国との新たな防衛関係が含まれている。日本は円借款を与える事でフィリピン国軍の増強を支持する事になっており、これには10隻の日本製沿岸警備艇の提供により、南シナ海にフィリピン海軍の存在感を高める事が含まれる。
その一方で、アメリカによるアジアへのリバランスに対する信用が大きく損なわれる事となった。これは、バラク・オバマ大統領の10月の東南アジア訪問が、アメリカ連邦議会の財政問題とその後の政府機能の一部閉鎖のために中止せざるを得なくなったためである。しかし最近、アメリカ連邦議会が超党派の財政協議で合意に到ったため、2014年の政府機関の閉鎖は回避される事になるだろう。これによって、オバマ氏はミャンマー(2014年のASEAN議長国)を訪問し、2014年11月初めの第二回 米ASEAN首脳会議と、ネピドーでの第九回 東アジア首脳会議に参加する事が可能となる。ミャンマーは、しきりに彼らが中国の良き隣人でありつつも、アメリカの新たな良き友となり得る事を示そうとしている。ミャンマーはASEAN代表国として、2013年から2015年のASEAN・アメリカ戦略的パートナーシップの調整にあたる。
アメリカ軍の南シナ海における存在の拡大は、中国との対立リスクを増加させるものだ。ごく最近、12月5日に米巡洋艦カウペンス号と中国の戦車揚陸艦が衝突しかけた事件は、カウペンス号が中国の空母、遼寧率いる海軍演習の動向監視を中国の要求通りに止めなかった事から生じたものである。
アメリカによるアジアへのリバランスや、日本の新たな安保上の積極的役割に対抗し、中国は東南アジアでの微笑攻勢を強化した。それには(ASEANによって受け入れられた)2010年の中国・ASEAN自由貿易圏をアップグレードさせる提案や、新たな善隣友好条約が含まれる。
既知の未知
さらに厄介なものは、我々が知らないという事を知っている、あるいは我々がその潜在的リスクを知らずにいる事柄である。おそらく究極の既知の未知とは、我々の太陽系の圧倒的神秘、どのようにこれが形成されたか、地球上の生命の起源(あるいは諸起源?)とは、そして、この太陽系が広大な宇宙の中でどこへ向かっているのか、というような事であろう。
南シナ海における新たな既知の未知は、中国の九段U字型線という、壮大かつ問題の主張に対するフィリピンの訴訟である。ASEANの加盟国仲間との事前協議もせずに、フィリピンは1月に、国際海洋法裁判所で中国に対する訴訟を提起した。5名の裁判官から成る仲裁法廷が組織され、この訴訟の検討に当たるが、中国はこれに加わる事を拒否している。いくつかの小規模な、あるいは短期的な既知の未知をこの訴訟に認める事ができる。
この法廷がこの事案のさらなる審議に管轄権を持つ事に合意するか否かは不明であろう。法廷がこの審議の管轄権を持たぬと判定するなら、それは中国の勝利を意味し、中国の九段U字型線への新たな訴訟が起き得ぬ事を意味するのであろうか。一方で、法廷がこれに管轄権を持つとの判定をするとして、フィリピンからの要求に対して、どのような裁定が下されるかは依然として不明なままである。中国はこれまで、公式に九段U字型線が何を示すか、明確に説明した事がない。そのため、法廷はおそらく、これについていかなる判決をも下す事ができないだろう。たとえ法廷が、中国が実際にフィリピンの海域を侵犯している、あるいは、フィリピンの排他的経済水域内の島々や岩礁を侵害していると判決したところで、どのように中国に不利な何らかの判決を実行する事ができるだろう。
この九段U字型線は、最も厄介な既知の未知の一つとして南シナ海に存在している。中国当局の人間が南シナ海に十一段の線を加えたのは、1947年に出版された地図であった。彼らは明らかに地図製作の細部にはほとんど注意を払わず、この十一の破線をいかなる地理座標に特定する事もしなかったのだ。これらが海上境界線として意図されたものであったなら、この十一段線は実線としてつながれ、全ての要所が正確な地理座標を備えているべきなのである。
1949年以降に中国の採用した中華民国の南シナ海地図は、この十一の破線を含んでいる。二つの破線がトンキン湾から取り除かれたのは、北ベトナムとの領海画定が1950年代のはじめに合意された後であった。目下、中国がその計算づくの戦略的曖昧さにおいて一枚上手であるのは、他の権利主張者たちが、九段U字型線が実際に何を指すものか、確信の持てぬままにしているためである。
もう一つの台湾にまつわる既知の未知は、タイピン/イトゥアバ島の軍事占領であり、これはスプラトリー諸島における最大の争点となる島である。中国は台湾軍の存在を容認しているが、その理由は不明である。
これは一つの中国政策の表れかもしれない。
もし、中国が南シナ海の係争領域に対する歴史的権利の主張の勝者となれば、その結果はどのようなものになるだろうか。これは懸念すべき既知の未知である。最初の大きな犠牲は、UNCLOSの解体であるかもしれない。他の主要諸国は、その他の場所で係争中の領土や海域を各自の歴史的権利の主張に基づいて強奪しようという気になるかもしれない。どこまで歴史を遡り、正当な主張の根拠と成す事ができるのだろうか。
結局、はるか昔に遡れば、我々は皆、同じ出自の人類なのである。
さらなる既知の未知は、南シナ海における自己主張をより強化するという中国の戦略的意図である。中国の主張は、この地域の領空通過や航行の自由が、合法的な無害通航権を行使するいかなる国の問題にもなった例がないという事であろう。しかし、中国はその200海里の排他的経済水域内における、外国の軍艦や航空機による軍事活動に反対し、時にはその妨害を試みようとさえしているのだ。
近いうちに、中国が南シナ海に一方的な防空識別圏(ADIZ)を設定するというのもあり得る事だ。
おそらく、パラセル諸島を手始めに、中国航空母艦部隊が配備計画を押し進める準備が整えば、南方のスプラトリー諸島へと拡大して行くであろう。アメリカのジョン・ケリー国務長官は、2013年12月17日のフィリピン訪問の際、中国に対して南シナ海にいかなる防空識別圏をも設定せぬよう警告を行った。
1951年の米比相互防衛条約にまつわる不確実性もまた、既知の未知である。アメリカはフィリピンへの軍事支援を増加させており、そこには12月17日にケリー氏がマニラで発表した、さらなる4000万米ドルの支援が含まれている。しかしアメリカは、万一フィリピンと中国との間に、南シナ海で深刻な武力衝突が生じた際に取りうる対応については全く曖昧なのである。おそらく、これはアメリカの戦略的曖昧政策の一環なのであろう。
中国が南シナ海の超えてはならぬ一線のありかを知らず、ただこれを推測するに止めておくためのものだ。
中国とアメリカの対立がどのように展開して行くかは、深刻な既知の未知である。この対立がすでに東南アジアに間接的な軍拡競争をあおっている事を見れば、安心してはおれない。この対立が深刻化すれば、その先に待ち受けているものは何であろう。新たな冷戦が世界の中の我が地域に生じるのであろうか。
未知の未知
未知の未知はリスクの中でも最悪の類のものである。なぜなら、我々はその存在すら知らず、それは重大かつ計り知れぬ衝撃で我々に襲い掛かり得るからである。場合によっては、一方がリスクを既知の未知として捉えていても、もう一方はおそらくそれに全く気が付いていない。それが未知の未知である。予期せぬ日本の真珠湾攻撃がその一例であった。この攻撃はアメリカにとっては未知の未知であったが、これは主に日本が国際法や外交規範を破ったせいである。同時に、日本軍は自らの行為を理解してはいたが、その攻撃の結果や、最終的に第二次世界大戦に惨敗する事は見通せていなかったのである。
南シナ海において、何らかの未知の未知の例えを思いつく事は困難である。
定義上、我々はそれが存在する事を知らないのであり、ましてやその結果を予見するなど、不可能な事である。
未知の知
スラヴォイ・ジジェク(Slavoj Zizek)は、マルクス主義の哲学者であるが、彼は人類にとって最も重要なことは、彼が「未知の知」と呼ぶものであると述べている。これらは存在し、我々の人生や現実理解の方法に影響を与えつつも、我々がそれを知っている事に気が付いていないか、その価値に気付いていない、あるいは最悪な場合には、それを知っているという事を我々が認めようとしない事柄である。
国家レベルにおいて、それぞれのASEAN加盟諸国は親中派であったり、親米派であったり、または中立であったりする。ところが、ASEANという一団として集まると、彼らはASEANを中立的で建設的なものとして保つ努力をして行くと言う。彼らはASEANが対話と協力の中心となり、あらゆる主要国に対して友好的である事を望んでいるのだ。
ASEANは中国や日本、大韓民国、そしてインドとアメリカをその「戦略的パートナー」としてきた。
ゴー・チョク・トン氏は、彼がシンガポールの首相であった時、このASEANの気まぐれを「道徳的乱交」と評したことがある。
ASEANの中立性と中心性にはどの程度の効力があるのか。また、それはいつまで続くものなのか。中米対立はASEANに深刻な分裂を生む原因となるのか、悪ければ、それはこの47年来の組織に崩壊をもたらす原因となるのだろうか。この懸念はASEAN加盟諸国の大半が、考える事さえしたがらない未知の知である。
もう一つの未知の知は、EAS(東アジアサミット)の首脳陣が、様々な島をめぐる論争の対応援助にしくじり続けている事である。南シナ海の事例とは別に、中国と日本の間には釣魚島/尖閣諸島、日本と大韓民国の間には竹島/独島、日本とロシアの間には北方領土/クリル諸島の論争がある。これらの島をめぐる論争は緊張の源であり、不安定を生じさせ得るものである。だが、これらはほとんどのEAS首脳陣にとっては、未知の知のようである。
結論
既知の知によると、南シナ海論争は、我々の地域にとって危険な問題のままである。これらを公平に解決するには、時間と政治的善意が必要であろう。だが、対話と協力、ASEANとの連携を通じ、全関係者たちが相互信頼を高め、新たな緊張を回避する事は可能である。優れたASEAN・中国の南シナ海における行動規範は、正しい方向に向けた大きな前進となるだろう。
もし全ての当事者たちが、南シナ海論争に利他的意図をもって取り組めば、実質的で公平な解決策を、譲り合いの精神で共に探る事ができるだろう。そうすれば、既知の知のリスクを最小限に止める事ができる。
彼らがここで分別ある行動をとり損ねれば、南シナ海に発生し得る壊滅的な不測の事態、ある日噴出して平和と繁栄を破壊するかも知れぬ未知の未知に、我々の地域をさらし続ける事になる。
そのような恐ろしい未来を回避するために、今決め手となる新たなスタート地点は、南シナ海論争には未だに未知の知が存在する事を、全ての関係者たちが認め、彼らがこれに対して際限なく知らぬふりをする事も、これを永久に棚上げしておくこともできないという事を認める事である。
行動すべき時は今だ。時間はどんどんと失われつつある。
Termsak Chalermpalanupap
Dr. Termsak Chalermpalanupap is a visiting research fellow at the ASEAN Studies Centre of the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) in Singapore. Previously, he had served nearly 20 years at the ASEAN Secretariat, where his last post before retirement was Director of Political-Security Directorate of the ASEAN Political-Security Community Department. Views expressed in this article are his personal opinions.
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 15 (March 2014). The South China Sea