
こうして、我々の演劇は、ある新しいものから別の新しいものへと移ろっていく。我々の前途には何が待ち受けているのだろうか?1970年代以前に存在していた、たくさんの規則から、我々の脚本家たちが一度は自由にしてもらって以来、予言はできなくなってきており、それを言うことは困難である。今日では、ただ一つだけの規則、すなわち、演劇は固定して動かない硬質なものではない、という規則だけが流布しているようである。しかし、自由と共に、重い責任が、特に広い心がまだ育っていない観客に対する責任が、やって来たのである。(1979年4月8日、Jit)
マレーシアのような社会環境、すなわち、(人種的、宗教的、加えて言語的に)異なった諸文化が、国家と共に、さまざまな権力関係の中で共存しているような場所では、パフォーマンスについて議論するという任務は、優越的な実践とその結果として生じる偏見を生み出すところの、社会‐経済的・文化的政策と絡み合うということをもまた、含意している。具体例を挙げれば、(民族集団別の不条理な所得格差を減少させることを目的とした)国家公認の差別是正措置と(マレー語のクレオール化による「不純化」を防止することを意図した)国家言語の使用と管理は、マレーシア人のディスコースを形作る、周期的に発生する論争点である。人種や宗教といった、文化の一定の側面が「センシティブである」と分類されて―すなわち、公共的な議論が公認されておらず、その限度を侵犯した時に重大な検閲がなされる―場合、アイデンティティや国民らしさに関する論争点とずる賢く取り組むパフォーマンスは、しばしば、網から滑り落ちるのである。
これらの場に対する慎重な注意は、批評と省察のための豊富な素材を提供する。しかしながら、批判的な分析が歴史への視点を提供し、芸術解読の技法を発展させるという思考の場を創出することへの挑戦が果たされることはめったにない。Krishen Jitの長く続いたNew Straits Times紙上の芸術批評コラムであるTalking Drama with Utihは、マレーシアの風土の中での、そんな場所の一つであった。それぞれのコラムは、パフォーマンス・イベントの批評のみならず、それに関連した論点を突く、巡り会いであった。これに肩を並べる関心と分析の深さを生み出している者が、もし他にいるとすれば、残念ながら、それは、ほんの二、三の例しかない。本稿は、Jitの批評するという選択の結果として―しばしば一つの記事の中で―伝統文化・現代的不安・同時代の切望との「出会い」を創り出した“Talking Drama with Utih”のいくつかを検討する。
“Talking Drama with Utih”(「Uthiと共にドラマを語りあう」)
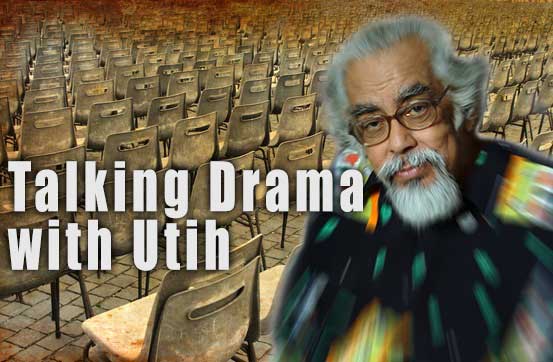 パフォーマンスの批評は、審美的な価値の評価を越えて、作品の背景となっている政治的コンテキスト(脈絡)と文化的歴史の探求へと及ぶものである。マレーシアのようなポストコロニアルな多元的社会においては、これは、選択肢を与え、反響を左右し、文化的容認の限界を決定するローカルとグローバルの双方の影響への意識的な自覚化を含むことになる。商品化されえないものとしてのライブ・パフォーマンスは、パフォーマンスの瞬間を越えた歴史的記録と反響については、批判的論評に依存する。これを実践することは、つかの間の一瞬を、洞察と出来事への感性とその意義を提供することになる、持続する記録へと置き換えるという、法外な努力を要求する。
パフォーマンスの批評は、審美的な価値の評価を越えて、作品の背景となっている政治的コンテキスト(脈絡)と文化的歴史の探求へと及ぶものである。マレーシアのようなポストコロニアルな多元的社会においては、これは、選択肢を与え、反響を左右し、文化的容認の限界を決定するローカルとグローバルの双方の影響への意識的な自覚化を含むことになる。商品化されえないものとしてのライブ・パフォーマンスは、パフォーマンスの瞬間を越えた歴史的記録と反響については、批判的論評に依存する。これを実践することは、つかの間の一瞬を、洞察と出来事への感性とその意義を提供することになる、持続する記録へと置き換えるという、法外な努力を要求する。
“Talking Drama with Utih”は、マレーシアの英語新聞の中で、最も長く存続した芸術コラムであると認められている。世に認められた演劇界の長老であったKrishen Jit(1939~2005年)は、1972年から1994年に至るまで、毎週、Uthi―マレーシア文学における桂冠作家であるUsman AwangによるUda dan Dara(マレー語:UdaとDara)という劇の登場人物の一人―という筆名を用いて、マレーシアにおける演劇と芸術について書いた。劇中では、Uthi は、彼の人間のありかたに関する洞察が事態を紛糾させるのだが、それにもかかわらず、思考を刺激してくれる能力によって崇敬されている、賢明だが一風変わった村の年長者である。Uthiは、常に慣習やしきたりを信奉せず、そして、後でしばしば彼のラディカルな考え方や強力な批評のために誤った解釈に陥る。いくつもの点で、Jitのコラムは、彼に似た役割を演じていると言えよう。
30年間に及ぶマレーシア人の生活の、大きな変化の中にあって、Uthiの声は、アイデンティティ、モダニティ、教養、芸術における公正といった論争点を探求する間に、多元的で分裂した社会のダイナミズムと深く関わってきた 1。不条理劇 2、もしくは中国歌劇 3として―彼自身の限界を認める自由さをもって、それ故に権威主義的に見えることなく説得的に―Jitはローカルなものを国際的なものと関連させて、あるいは、その逆もまた同様に、解釈して提示した。彼は、自らの役割を、選択の贅沢さが、気まぐれな思いつきで選んだり拾い上げたりすることを可能にする、ブロードウエイやウェストエンドの評論家とは区別されるものだと理解していた。Jitは、マレーシア人の批評家は、時に、それが、進化しつつある一つ国民文化と特徴付けられるものとして、ローカルな実験を理解する困難な任務をやり遂げなければならならず、そして、それは作り手と観客の両方の利益のために議論されるに値するものだと信じていた(Jit、1986:5を見よ)。これは、なじみの無いものに注意を払い、自らの本能を信用し、客観性と絶対的な権威への誤った信頼に対してはっきりと挑戦することを意味する。
あなたがそこで使用されている言語が分からない時であっても、いかに多くのものを見たり聞いたりできるかということは驚くべきことである…まだ慣れていない人は、その場ですぐにコード化されたメッセージを解することはできない。また、舞台の袖でも続くようなジェスチャーの中に込められたニュアンスをきちんと理解することは不可能である…たとえ仮に、ため息の意味を知らなくとも各自の理由によってそれを楽しむことは可能である…だから、もし広東語を知らないとしても広東歌劇を見に出かけよう(Jit、1986年5月25日)。
“Talking Drama with Utih”は、パフォーマンス批評以上のものを行った。そのタイトルが示唆するように、それはJitが文字通りその一部であった活動、すなわち、「ドラマについて語った」のである。パフォーマンスのほか、芸術を製作・鑑賞・支持する人物・政策・状況について議論したのである。想像を分かち合うこれらの「会話」は、限界にまで及び、オルタナティブを力づけ、「歩くこと」そして「話すこと」の演技にも影響を与えた 4。意義深いことに、「ドラマ」は、通常の舞台演劇の観念を越えて、束縛を超越した、多角的様式のパフォーマンスや芸術イベント―すなわち、一流のミュージカルから素人による詩の朗読まで、あるいは、活気のあるシャーマニズム的な悪魔祓いの儀式から無意味なダンスの上演レパートリーまで―拡張されて、そのおのおのは、マレーシア文化の複雑な混交を増加させている。無数の枠組みと多様な形態を次々とシフトしていくという、Jitの生来の性癖は、一本一本の糸の場所を確保しながら、異なった素材を編み上げていくことの必要性への自覚と、うまく調和していた。
Jitの理論的パースペクティブと実際の経験に基礎を置いた洞察力は、歴史家としての訓練と、現在進行中のいくつもの芸術表現の消費と、パフォーマンス研究の分野に関する自己教育とを軸とするものであった。これらは、現代化しつつあるマルチエスニックな庶民を抱えつつ、急速な変化のもたらす矛盾と不確実性と格闘しながら、文化的整合性を生み出すことを希求している若い国民の中でのパフォーマンスを解釈するには決定的なものであった。これは、1969年5月に起きた、非常事態統治と文化・教育・経済に関する国家政策の劇的な軌道修正をもたらした、首都クアラルンプールで発生したマレー人と中国人との間の未曾有の民族暴動の結果、国内中が混乱状態にあった1970年代早期には特にそうであった 5。この暴動は、Jitに英語での演劇製作を断念させ、流暢なマレー語の学習を決意させることとなり、それによって、彼がいまだ取り組んだことのないマレー語演劇(MLT)への参加を可能にしたのであった 6 。主として英語演劇(ELT)に関わりつつも、MLTへ参加し、さらには多言語演劇にも関わるという選択は、文化とアイデンティティという、自らの技能によって創造し、交渉することになる分野に彼を置いたのである。
Jitの論評の政治学は、率直さと共に明瞭に示されている。彼は、たとえ仮に製作の美的側面が彼を常に喜ばせたわけではなくとも、文化のローカルな製作に興味を示し、実験的な試みに対して興奮し、既知のものと未知のものとの間の連繋を鍛える努力に拍手喝采し、危険と冒険のセンスを奨励した。本稿では、Jitが繰り返し議論し、マレーシアの芸術分野において核心として残されている3つの分野について焦点を当ててみたい。つまり、同時代的実践と統合することを通じた地方的伝統と民俗的表現形式の再活性化、プロフェッショナリズムを強化し製作を美的に深化させていくための国内芸術家たちへの批判的養育、そして反響を持続させ尊敬を勝ち得るために社会‐政治的な変化へと対応していくこと、の3点である。
伝統と同時代の実践を統合すること
伝統的であろうと現代的であろうと、芸術表現形式の妥当性とそれに対する反響は、急激に変化しつつある文化の中では決定的なものである。マレーシアのような現代化しつつあるポストコロニアルな国家では、過去の値打ちを政府が決定するか、現代の不安にとりつかれるか、という性向は深刻である―そして、公共の関心が持続することを助けることも国内の芸術家性を建設することのどちらも行わない。この環境の中で、Jitは、伝統的で民俗的な表現形式が、それらの独特の存在をできるだけ残したまま、現代的な表現手段の一部になることの必要性を、しばしば論じた。これは、より広範なコンテキストに反応しながらも、ローカルな歴史から汲み出された土着の仕事の生産を奨励するものであったろう。社会の中に、それらが優勢で公式に存在しているのにもかかわらず、Jitは、そうした本質化された規範に抵抗しつつ、一緒に何かを創りだしていくような共存への統合された表現を手助けする擁護者と熱狂者を引き付けるような、(伝統的な、現代的な、マレー系の、中国系の、インド系の、西洋系の、規範的な、実験的な、地方的な、世界市民的な)異なった諸文化間の連携を希求していた。
マレーシアで行われた中国歌劇公演のまれなテレビ放映を論ずるなかで、Jitは、真正性と翻訳の論点を提起した:
ある人々は、中国歌劇が他の言語で上演された時には、その生命に関わる何かが失われてしまっていると主張するであろう。これと同類の純潔主義者たちは、wayang kulit[マレー語:影絵芝居]の上演が、方言からBahasa Malaysia(マレー語)の標準語に転換した時に、当然の帰結として生じた秘伝の技(art)の消失を嘆き悲しんでいる。演劇あるいは他のいかなる芸術であっても、言語の移し変えが、危機と危険をはらむものであることに疑問の余地は無い…(他の)言語で道化を演じることはできない。パフォーマンスにおける即席の言語の移し変えのいかなる観念も、最後は、確実に、芸術を損なうことに成り果てる。けれども、言語を取り替えることの危険に打ち負かされるままになっていることはできない。19世紀に、ヒンドゥー語のParsi(古代ペルシャのゾロアスター教系のペルシー教徒の?)舞台演劇が、Malay bangsawan(マレー式の軽喜劇)に移し変えられた時には、はるかに困難な熟慮と仕事が成し遂げられなければならなかったこと(を思い起こして、それ)に賭けてみるべきである(Jit、1991年2月24日)。
ここでJitは、変化の必然性について注意を喚起し、論点を生存の可能性に関わるものに結びつけている―つまり、言語使用の問題をパフォーマンスの表現手段の拡張と関係付けている。彼は、幾世紀にもわたって文化の交換が出会う地点であり続けてきた場所で、異文化遭遇によって常に影響を受けてきた存在の持つ価値を断言し、結果として起こる「危険」に向き合う勇気を持つべきであると示唆している。
ロマン化された過去の謎めいた魅力を認めつつも、Jitは、神話と記憶の遺産へのアプローチへ疑問を投げかけて、変化を喜んで迎えるために成功しそうな戦略としての文化適応の必要について論じた。彼は、僅かしか文化が尊重されていないことと研究された結び付きengagementの不足を反映している、うわべだけの伝統要素の取り込みを嘆いていた。Jitの熟考は、地方の伝統と民俗的表現形式を同時代の実践の内部に統合することの必要に焦点を絞っている。(文化の非植民地化と土着の表現形式の発展をめざす)ポストコロニアル・スタディズと、(グローバル文化と諸民族間の協働を志向する)パフォーマンス理論の双方の解読に影響されて、Jitは、化石のようにとらえられた文化の観念に抵抗した―つまり、非植民地化された国民の複数的自己同一性を鍛え上げていく過程の共通する傾向―そして、西洋に教導された多文化間協調主義interculturalismの偽装の下での、「東洋の他者」のエキゾチック化への用心深さを示した。
刺激的な新しい試みとして、頻繁にインドネシア演劇に言及しつつ、Jitは、ジョクジャカルタに本拠を置く劇団、Teater Gandrikの「自由に即興で演じ、最新の出来事を描きながら、しかもパフォーマンス・メディアがその物語を語る」存在でありながら、「順応性のある民俗環境のなかにしっかりと根をおろす」能力について、熱狂して語った(Jit、1990年)。彼は、1990年にシンガポールにおいて開催されたASEAN(東南アジア諸国連合)演劇祭でのGrandrikのDemitの公演について、「愚かで粗野な、しばしば大衆文化の資源から流用された」ユーモアのある「活気と機敏さ」として、これが、物語とメッセージをつなぐ橋となっている、と描写した(同上)。これをJitは、次のように説明した:
Gandrikは、伝統の中にどっぷりと身を浸してはいるが、同時に演技者たちは、現代の大衆のまっただなかにいるという波動を持っている。彼らの本拠は、戦略的に、町と国の十字路、古くもあり新しくもある場所、に位置しているのだが、これが、伝統と現代とを橋渡しする彼らの機敏さを説明する。
Jitは、明らかに、Grandrikのマレーシアにおける同僚たちが、同様の結果を達成するために努力するだろうという希望を持って、これらの特質と戦略に光を当てることを選んだのである 7。
国内の芸術家たちを批判的に養育すること
拠って立つべきものを見出そうとして格闘している若い国では、彼ら自身を包み隠すもののない、外見上はか弱い芸術家たちを論評することは、不快なことであると思われるかもしれず、したがって、拒絶される危険をおかすことである。しかしながら、公開の対話によるこの成長過程なしには、芸術家は、その中で、自らの仕事を反省し感受性を強めていくための、批判的な環境を欠くことになる。批評を嫌がることは、鑑賞の政治学を身に付けた観衆と結び付くという課題と重層的文化環境を無視することにもなるが、批評は芸術への非受動的な応答を奨励する。Jitは、これを「慇懃無礼に」なること、そして芸術家、特に若い芸術家、とは何であるか、を白紙に還元することであると理解し、実行できた(Jit、1992年、日付不明)。
実践者たちの小さなコミュニティのなかにあって、実践者と批評家を兼ねることにより、Jitは、公開の対立と批判的な対話に不慣れな文化のなかで、同僚たちと友人たちを論評するという危険な立場を取ることになった 8。これは、Jitのタフな態度が、批評の原則の一部として認められなかった時に、時折、敵意を生み出した。同僚の実践者で批評家であったKee Thuan Chyeは、例外の一人で、1970年に上演された彼の最初の演出をJitが、いかに「ほとんど木っ端微塵に」酷評したかを描写しつつも、「彼の書いたものや意図のなかに、悪意はひとかけらも無かった」と認めている(Kee、2005年)。
彼が身近に関わっていた仕事、すなわち、Five Arts Centre(1984年に彼が共同で設立した映像とパフォーマンス芸術の集団)について、Jitは、決して書くことが無かったにもかかわらず、彼がその一部であると見られることは避けがたかったので、親しくない部外者からは、不公正さを責められていた 9。ローランド(2003)が指摘したように、Jitのバイリンガルな学者であり、批評家であり、政策立案者であり、実践者であるという特別な立場は、「拒否することが困難な、釣り合いがとれないほど高い水準の正当性」を結果し(18)、そして、これが、「あいまいであるとか、オルタナティブな見方を蝕んでいる」という理解を導き(同上)、より一層の憤怒や不快感をかきたてることになったのである。
それでもまだ、Jitは、限界を乗り越える必要や演劇への関心をかきたてることが必要だと感じた時には、刺激し続けることができたし、当然それが賞賛されるべきだと感じた時には、賛嘆を抑えることが難しかった:
Jit Muradは、我々の同時代のpenglipur lara、ここ、今の社会的、個人的風俗に関する物語の語り部であり、我々の神経症を慰めてくれる存在である。彼は、物語を語りながら、熱に浮かされて火照る…笑いは、我々を、マレーシア人としての我々の意識の中に打ち込むための彼の武器である。しかし、それはまた、非難と彼の属する時代と時の欠点に対する、彼の暴発しやすい憤怒を秘匿している彼の鎧でもある…それは、ほとんどが西洋で教育された若い都会のマレーシア人のグループに特有な懺悔の時期である。Jit Murad作の『ひょう嵐と金色の雨』は、確かに、大空で最も輝いている星である(Jit、1993年、11月28日)。
Jitは、たった数年前には、Muradを献身的であるよりも、むしろ「冷淡な」「自己陶酔世代」の一部と見なしていた(Jit、1989年、日付不明、を見よ)。
Jitは、発展すること、現代化すること、そして、批判的であり意見の相違や対立を恐れないことで、芸術的表現を真剣に受け取ることを必要とするコスモポリタンになること、を希求する国民について主張しながら、フランクで開かれた態度で書き続けた。彼は、因習から訣別し、新鮮な土着の表現形式を鍛えあげた実践者の大いなる志に注意を喚起した。彼は、特に、露骨に無視されているか、その意義を軽んじられている環境の中で仕事に取り組んでいる芸術家たちに向かって光を当てる準備をした。彼は、1970年代の農村‐都市間の移動に抵抗する不安、現代化しつつあった1980年代のアイデンティティの相克、富裕化した1990年代早期のコスモポリタン的野望、といった生成しつつある傾向を反映した作品を注視し分析することにポイントを置いていた。
国民的コンテキストの中に彼らを位置づけながら、芸術家たちによって行われた選択や取られた方針へと関心を向けることで、コラムは、その仕事を尊重していた。Mustapha Norは、美学と政治的立場の相違にもかかわらず、Jitにその仕事を印象付けた犀利な人物である。Norは、Jitとは異なり、西洋的リアリズム演劇を好み、彼のエネルギーをそのスタイルの作品を作ることに捧げたが、Jitは、マレーシア演劇の水準を引き上げようとするNorの粘り強さと献身は、大きく評価した:
Mustapha Norは、マレーシアにおける演劇人の、新しく形成されつつある世代に属している。彼とその友人たちにとって、演劇とはとてもシリアスなものなのだ。それに結び付くことは、高い職業的矜持を要求し、それに値する公衆へ、良質な演劇を提供することへの欲求が生まれた。陽気な観衆に向かって暇な時にやる道楽としての演劇は、Mustaphaと、その同僚の人々にとって、過去のもの、あるいは、そうなるべきものである。自らの作品に対して、同じように強烈で非妥協的な立場を持って臨む多くの演劇人が、今日では存在している。しかし、そのような道理にかなった包括的なやり方で上演される演劇に近づく人々は、ごく僅かなのである。
新鮮なエネルギーと様々な創造性の活気を楽しみながら、Jitは、持続性と質の問題も提起していた―すなわち、演劇の潜在力と位置づけについての、より厳密な分析と批判的な検討を推進していたのである。彼は、芸術家が成長していくための機会を提供する必要について繰り返しはっきりと述べ、作家を育成し、俳優を教育し、製作者をプロ化するために、もっとプロフェッショナルな訓練や資源を増やすことを強く求めた。この点に関しては、Jitは、公衆の目の前で健筆をふるい、真剣に場所を割いて、影響を与えた。彼は、芸術作品のための状況を向上させるために当局をせっつきながら、それが、違いを作るために闘った人々を激励することを望んでいたのである。
それにもかかわらず、演劇と芸術製作の諸問題は、まだ停滞していた。1970年代に出版された国内演劇の欠乏を嘆きながら、Jitは、こう書いた:
我々は、自分たちのごく近い過去にさえもほんのちょっとしか注意を向けないままの演劇文化を持っている。出版された演劇の不足によって、我々の監督たちは、より古いドラマの永続性をテストすることができない。何もかもが観客にとっても新しく、彼らの好みは、目新しさに向かってギアを入れられている…Noordin とHassan Syed Alwiの存在は、我々の発明の才が全て失われてしまったわけではないことを示唆してはいる。しかし、我々の作家たちが、我々に与えてくれる、我々自身の洞察を、宝物として蓄えなかったならば、いずれはそうなることであろう(Jit、1976年8月8日)。
1980年代中葉には、Jitは、さらに懸念を深めていた、すなわち:
我々の演劇は、ますます機動性がなく閉所恐怖症的になりつつある。実験的な1970年代を特徴付けた、上演のための新しい空間と新しい観衆の探求は、最初はうまくいったが、結局はドジを踏んだようだ。今日の演劇は、狭い観客席の安楽で用心深い領域と…馬鹿でかい上演空間と…都市部の中産階級の観客を躾ける[ために]…ほとんど全く限られてしまった…演劇人にとってのみ魅惑的である、絶え間の無い騒音を出す仕事に成り果てることから演劇を救うために、演劇が雑多な観衆を必要とするということは、神様がご存知だ。
彼は、芸術家たちに、あてもなく漂っているだけではなく、刃を研ぐために努力するように督促を続けたのである。
社会‐政治的な変化に対応していくこと
“Talking Drama with Utih”の連載期間中に、マレーシアは、政治的、社会的、文化的風土の急激で劇的な変化を見た。新興独立国の、1960年代と1970年代のおおむね農業に基礎をおいた経済から、わが国は(特にその首都において)、1980年代と1990年代の都市の「新富裕層」によって牽引された、急速に成長する工業主導型の現代化の連関に巻き込まれていった。国家が旗振り役を務めた外資を誘引するための自由化政策と、増大する自由化は、社会‐文化的な変化と引き換えに、起業家精神と多様化を促進した。そういった変化のなかの一つは、文化資本を生産し、消費したいという欲望であり、グローバル化した主要都市でのコスモポリタンな生活様式の模倣であり、前代未聞の規模での芸術に対する後援と保護であった。しかし、これらの資源の管理と分配は、大部分、欲望のなすがままに放置された。
マレーシアにおける芸術後援について語られる時にはいつでも、もし深い絶望でなければペシミズムが、その議論を動かしている…企業が芸術の発展に興味を示さないことについては、芸術の合理的計画と実行に向けての政府の不変性に大きな責任がある。政府がスポーツに旺盛な努力を向け、有権者を獲得しようとする時には、企業体は、その太鼓持ちとなって協力する。彼ら自身としては、…ミュージカル、それもできることならば外国から輸入された創造的な内容をふんだんに含むものにだけ賭けをする…このような後援のあり方は、国内のパフォーマンス芸術家たちに屈辱を与えている(Jit、1990年8月5日)。
Jitはこれらの変化について議論し、そして引き続いて起こった可能性に、喜んで反応する必要について論じたが、芸術家たちがもっと想像力豊かに応答することの必要もまた認識していた。Jitは、芸術イベントに資金を出し、新しい場所を開発することへの国家のイニシアティブへ拍手を送ったのと同じようにたくさん、どうやったらプログラムを向上させて興味を持続させられるかについての考えもまた提示している。全体として、もっと「発展した」社会になるための努力と同時に、芸術は国民形成のために決定的な分野であることが認識 される必要がある。そして、少数の実践家や官僚だけがこのことを理解していた 10。
ASEANとしては、貿易関係を育成し、地域を横断する政治的結合を発達させたのだが、Jitは、東南アジアの実践者たちとその集団(例えばインドネシアのArfin NoerやタイのMAYA)に照明を当てて、彼らの土着の現代的表現形式を発展させる能力や、社会意識への影響を検討していた。地方的な惰性と自己満足に対抗するために、Jitは、もっと政治的で鋭利な介入を動機付けるであろう類似点と差異を認定しており、PETA(フィリピン教育劇協会)のような実例が、もっとラディカルで、もっと衝撃の少なくない演劇に霊感を吹き込むことを望んでいた(Jit、1985年2月24日を見よ) 11。
才能の発掘と育成をもっと広くすすめることの必要性を強調しながら、Jitは、正規の教育課程での芸術教育、コミュニティでの芸術実践への援助、民間と公的機関との間のパートナーシップについても主張を展開していた。これらは、芸術運動が、「マレーシア観光」タイプの浅薄な文化的自己満足を越えていくことを助ける妥当なインフラストラクチャーと補助的環境の形成に貢献するはずであるし、長期的で持続可能な芸術運動の進歩を保障するのである。
ドラマは、学校教育の正規課程として教えることができるし、そうすべきである。かつては、パフォーマンス・アーツは毎日のなかの出来事であった。カンポンの子供は、歌い、踊り、演じることを自然に学んだものだ。現代的感覚の子供たちの演劇は、農村文化の分解の当然の結果である。今日の多くの国々は、ドラマに対する興味を育てるために学校のなかでの明確なプログラムを工夫してきている。それは、たくさんの機能を持つことができる。演劇の中でパフォーマンスを演じることは、それ自体で学習の過程である(Jit、1972年1月21日)。
芸術同業団体の緊急の懸念に回答するために、コラムは、法外な額の娯楽税や、不条理な検閲、心無い管理についても論争を行った。彼の声は、借金しないでいるための闘いが、しばしば公衆には見えない状態にとどまっている実践者たちの利益のために発言した声であった。それは、芸術を活気に満ち、生存できる状態に保っておく闘いに参加していることをほとんど意識化していない観客に対する啓蒙であった:
我々は、公共空間でのパフォーマンスに関する実に多くの規則を持っており、演劇とは、結局は上演されたものだとすると、それは不思議なことである。これらの規則が暗示していることは、劇団は、お金を持つべきであり、安全な劇を上演すべきであり、人脈を養うべきであり、その全てを超越して、ますますはびこりつつある官僚制と取引する分別を持たなければならない、ということである。もしも、仮に、あなたたちが、文化‐芸術‐観光省から、もしくは、それ以外の権力のある公認された公的機関からの後援を受けたならば、そいつらは、あなた方のために官僚仕事をやらかしてくれるだろう。そういうわけで、別に驚くほどのことではないのだが、民間の企画である英語の演劇は、完璧なエリート主義に陥る傾向があるのだ。
結論
1986年には、Jitの演劇に関する記事の集成がマレー語に翻訳されて本として出版され、1970年代から1980年代早期の仕事の有用なドキュメントを提供している。これは、MLT、すなわちMembesar Bersama Teater(Growing Up With Theatre演劇と共に成長する)、に焦点が当たっているとはいえ、Uthiのより幅広い論点と非マレー・パフォーマンスに関する熟慮の幾つかが含まれてはいる。それは、その種の出版物としては、いまだにマレーシアで唯一のものであり、特定の時代と場所に対する計り知れないほど貴重な洞察を提供している。
彼自身による前書きの中で、Jitは、1980年の、それについて書くという重荷を背負うことなく貪欲に演劇を消費したニューヨークでの研究休暇から帰った後に、評論を続けていくことに気乗りがしないことを告白している。しかし、彼のつかのまのメディアの批判的な記録作業の必要性に対する信念と、しだいに成熟しつつある文化の中でのそんな努力の不足が、彼が躊躇に打ち勝って、自らの役割を再開することを納得させた。1992年には、Jitは、もはや風潮は変化し、「国内における演劇評論の高い意識」が既に発展した、と感じた(Jit1992)。そこで、彼は、1994年には常勤で大学で教えることから引退し、批評家としてのペンを置き、彼の注意を演劇監督に捧げることを決意した。
自らの早期の仕事を論評して、Jitは、演劇について書くことによって演劇を学ぶ機会を得たことに価値があったとして、「演劇とともに成長すること」と評論家の生き方を描写している。彼は、より早い時期の自らのパースペクティブの限界を認識して、自らの批評を批判的で綿密な目で再検討していた。それにもかかわらず、Uthiの発言を他から際立たせているものは、彼が議論した素材の幅広さであり、その職業に絡む「危険」にもかかわらず、演劇について書くという彼の献身ぶりである。
それが、境界を打ち壊して文化的な、また美的感覚の違いを称揚することを助け、本質的に異なるものと考えられてきたものを関係付けたことは、人種的分裂と文化的偏見にいまだに悩まされている社会においてコラムがもたらした不朽の効果である。「(聞いていようがいまいがおかまいなしに)一方的に語るtalking at」支配的な声のみを聞くことができるだけの方向へとますます針路を変えつつあるグローバルな環境の中で、「共に語り合うことtalking with」によって以上を実践しようとしたこともまた意義深いことである。その結果としてUthiの発言は、響き渡り続けるのである。
1月は、願望と決意の時である。現実には、マレーシアの演劇評論家は、些細なことしかできない。毎年の1月に低下する劇場のなかの鼻をつく乾燥によって悩まされて、評論家は将来のための計画と公約について語り合うように訴えることができるだけである。私には、それにもかかわらず、今年は、一つの願望と決意があるのだ。私は、私たちの時代の深い社会的な、そして政治的な問題に切り込む演劇が見たい。ほんの二、三の演劇人のみが、観客がじっと座り込み、己自身を凝視するような原因となる劇を演じようという考えを抱いている。私たちは、娯楽活劇の時代、高価な演劇の時代、職業化した演劇の時代に生きている。すべては公約であるが、ほんの少しだけがとりわけて成功してきただけである(Jit、1986年1月)。
Charlene RajendranはシンガポールのNanyang工科大学で演劇を教える。10代の頃から、マレーシアのパフォーマンス・アーツに監督・演技者・司会者・作家・製作者として関わり、マレーシアのFive Arts Centreにも参加。
Notes:
- Jitは、マレー語でも批評を書いた。1974年から1976年の間に、彼は、マレー語の新聞であるBerita MingguをSyed Alwiの演劇、Alang Rentak Seribu(マレー語:千のリズムのAlang)の登場人物であるAlangという名を使って記事を書いた。Jitの演劇記事は、地方の雑誌(eg.Tenggara、Asian Theatre Journal)にも、国際的な芸術関係の出版物(eg.The Cambridge Guide to World Theatre)にも見出される。これらによって、彼は広く知られる批評家の地位を得た。 ↩
- 1970年代の実験演劇は、マレーシア人の生活、特にマレー系マレーシア人の生活、の中で身についていた基本的価値観を取り除いた演劇の上演を含んでいた―DinsmanによるBukan Bunuh Dri(マレー語:自殺するな)は、とりわけそうであった。これは、その中で、神の観念や聖なる目的が、謬見の一部として暴かれている、西洋の不条理主義者の演劇の模倣とみなされ、彼らはその代表とされた。Jitは、第二次世界大戦後のヨーロッパの不安を経験したことがない文化的コンテキストにおける、宗教的異議申し立てのマレーシア風の表現を読み解く必要を強調することで、これを否認した。引用すると、「それら(脚本)のほとんどが奨励しているもの、そして、劇の主題と感動的な皮肉を考えると、基本的な不条理命題を支持することは難しい。それは、例えば、不条理の国内版に、命と息吹をあたえる実存主義ではない。一つの点で、我々のほとんどの台本の立場は、将来についてはるかに楽観的であるし…彼らの宗教的態度と、最も重要な点はこれだが、彼らの信仰の確さは、根本的に、彼らを不条理のジレンマから遠ざけるものである」(Jit、1979年8月8日参照)。 ↩
- 20世紀前半には、中国風の大道歌劇とBangsawan(マレーシア風の軽演劇)はコミュニティで人気のある催し物であったが、テレビと現代劇の到来とともに、これらの表現形式は衰えてしまった。これらを、再び大衆文化と結び付けようと企てて、関心を喚起し関連を作り出すために、Jitは、いかなる機会でも利用しようとした。1984年にニューヨーク・メトロポリタン・オペラがクアラルンプールで公演を行った際に、訪問している劇団について論じる前に、Jitは、コミュニティの生活にインパクトを与えた「国内オペラ」について書いた。彼はまた、国内の至宝の生命を無視しているのに外国のショーに喜んで大金を支払う観客の意図に疑問を呈した。 ↩
- 何人かのマレーシア人芸術家と製作者たちは、コラムが彼らに影響を与えたことと、それが、どのようにマレーシア演劇と芸術実践に対する彼らの理解を形成したかをほのめかしている。1980年代早期に、Jitが研究休職中で不在であった間に評論家の役を務めた、監督・脚本家・俳優・批評家のKee Thuan Chyeは、Jitの文章について、「より広い歴史的視野」を持っており、マレーシア演劇に対して「脈絡と方向付け」を与えたものである、と書いている(Kee、2005)。芸術プロデューサーでオンライン芸術雑誌であるkakiseniの共同創設者であるKathy Rowlandは、Jitの晩年に彼に会っただけであるが、「Talking Drama with Utihとともに成長したので…私たちが実際に友人になった時より何年も前に、彼について知るべきことは、もう知っていたように感じていた」と書く(Rowland、2005)。意義深いことに、kakiseniは、マレーシアにおける芸術評論と記録のために、最近ではますます重要なサイトとなっている。(http://www.kakiseni.com/を参照。)しかし、多分、最も興味深いことは、2005年のJitの死去の後に、マレー語の新聞Utusan Melayuに寄稿する評論家であるKu Seman Ku HussainがJitの特徴について書いたが、彼は、舞台監督Krishen Jitの仕事について論じる前に、批評家であるUtihを読者に紹介したのである。これは、コラムが終了してしまってから長い年数が経過した後にも、Utihの重要性が続いていたことを示している(Ku Hussain 2005を参照)。 ↩
- 5月13日の事件は、明らかに、植民地支配から自己統治と独立への調和のとれた移行を荒々しく破壊した。明白であったことは、差別的な政策と偏向した政治の欠陥と問題点にもかかわらず、マレーシアの概念を信じる人々による「国民」を創設する深刻な必要性であった。人種集団別の、またその各々の内部における政治的権利の剥奪と経済的な格差が人種間の暴力の中心にある中で、文化的、社会的事柄は、これらの深い傷を癒すために不可欠だった。それ故、芸術は、亀裂に橋を架け、マレーシア人であるためのオルタナティブな途を表現することに対してある重要な役割を果たす潜在力―つまり、人種的、宗教的、言語的な障壁を超越することを企てること―を持っていた。Jitのコラムは、これを実行するための場の一つであった。 ↩
- Jitの演劇実践者としての経歴の特徴は、政策と社会的趨勢の変化に対応してポジションを換えて新しいものを創り出すことにあった。MLTが、その志向において、露骨なネイティビスト(土着主義者:マレー系の出自の優越を主張することか?;訳者)となり、Jitが非マレー系であるという理由で彼の参加を拒絶するようになった時、彼は、土着の感性に染まりながらも,1980年代には英語演劇(ELT)へ、それから1990年代には、さらに多言語で異分野横断的な多角的様式の枠組みへと移行していった。これは、時代にあった適切なものとして生き残り、舞台監督、製作者、教育者として時代の趨勢に共鳴しながら作品を発展させていくために、異種のものを歓迎する必要への信念と、ローカルとグローバルな変化に対応して変化しようとする意思―彼の演劇における40年をこえるキャリアを通じて彼の作品に刻印された特徴―を示していた。 ↩
- 国内の舞台については、Jitは、「現代の観客のための土着化された舞踊劇の創造のお手本」としてAzanin Ezane AhmadnのSuasana Dance Companyを挙げているが、その理由は、「彼女のパフォーマンスの水準は高く、彼女が取り組む事柄や物語は徹底的に調べ上げられている上に、彼女は、舞踊、音楽、衣装、そして小道具にいたるまで、選び抜かれた最上の土着の構成要素のみを使用している。最も肝心なことは、彼女が、現代の観客には何が効果的であるかについての確かな本能を持っていることである」(Jit、1990年1月28日)。 ↩
- Jitは、この状況について、世界は「とても個人化されて、優秀な評論家は、短期間の割り当てられた仕事の後には、それを放棄することを無理強いされている」と記述している。 ↩
- Rowland(2005)は、Jitが「家の物置の引き出しに、長年にわたる個人攻撃の記事と手紙がたまっていると私に言った」と書くことで、これをほのめかしている。 ↩
- Jitは、「政府の高官が、この国の芸術と芸術家を救済するための公正な闘争に参加することは…めったに無いが…財務省の事務総長であったTan Sri Zain Azraai Zainal Abidinは、厳格で陰鬱な風土の中で、芸術にとって最良の途について話し合うことを捜し求めるプラグマティスト(実用主義者)の立場を取った」(Jit、1990年8月5日)と述べている。Tan Sri Zainは、国内の芸術分野を援助することの必要を理解した政府関係者の一人で、消費者とパトロンになることで、時間と資源を分配することを望んでいた。 ↩
- 1980年代のJit自身の演劇実践は、シンガポールに本拠を置く劇団と芸術家たち、主としてTheatreworkとOng Keng Senとの共同制作を含み始めた。彼に対する追随者から、マレーシア演劇への「裏切り者」とみなされながらも、これもまた、単純な「我々と彼ら」の分極化によって満足して仕事することなく、Jitが取り組んだ、もう一つの境界の拡張であった。シンガポールの演劇は、内容において、政治的に敏感ではなかったかもしれないが、表現形式においては、冒険的であったことは確かで、国家からの資金援助と職業的に訓練された実践者の利益を享受していた。彼の舞台監督としての最後の数年間に、Jitは、いくつかの公演をシンガポールで監督し、クアラルンプールの彼の家から、そこへの旅を定期的に続けていた。 ↩

