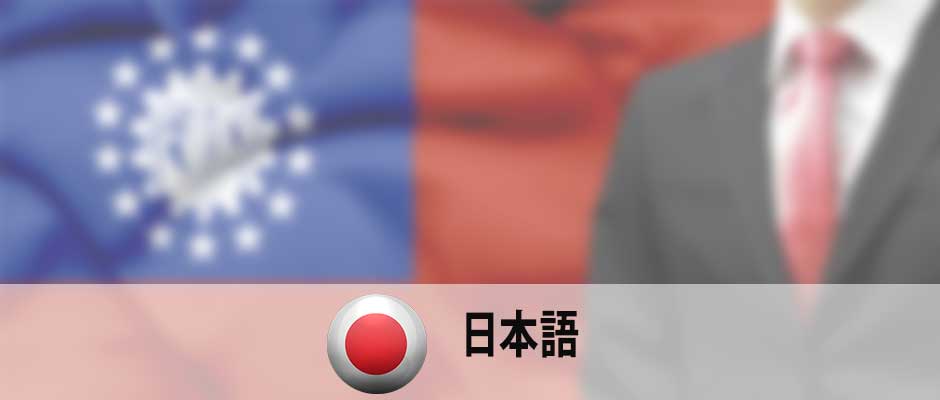序
近代西洋の統治理論と実践は、良き政府を軍部が文民統制の下に置かれた政府と規定する。共産主義諸国でさえ、党が主導権を握り、軍部がこれに忠実に従って国家のイデオロギーを、たとえそれが現実よりも虚構に近い場合であっても順守する。
いくつかの非西洋諸国では、例えば日本がそうであったように、この信念がしばしば苦い経験の後に根付く事となった。1989年にはミャンマー国民民主連盟(NLD)までもが、党の網領の一環として、文民統制の下にビルマ軍を置く事を提言し、1962年以来の軍部上層から忌み嫌われる事となった。だが、民軍のスペクトルの二極間にある二元論的感覚は、常に複雑に絡み合う一連の関係性に対する単純化されたアプローチとなってきた。
ところが、ビルマ/ミャンマーでは、独立時や民政下(1948-1958, 1960-1962)の軍部の役割が、西洋でのそれよりも、はるかに文民統制に非従属的であった。独立運動におけるビルマ軍の役割の現実や作り話がどうであれ、軍部が国家をまとめ、短期間で国の大部分を巻き込み、ラングーン郊外にまで迫ったカレン族の反乱に対抗した事には疑問の余地がない。軍部は多くの政治的(二つの共産党の)反乱や、様々な民族的反乱と戦った。さらに軍部は、無力な反ファシスト人民自由連盟(AFPFL)が、同胞同士の相争う1958年の内戦に加わろうとするのを止め、1962年のクーデターによって国家をまとめたことを主張、軍部が構想、支配するビルマ社会主義計画党(BSPP)を設立した。国軍の長(ネ・ウィン将軍)は、防衛大臣でもあり、一時は副首相でもあった。文民政権は極めて無力であることが判明したのだ。1988年の軍事クーデターは、軍部の支配下にあって破綻したBSPP政権にてこ入れをするために講じられたものであったが、この政権はこのようにしてtatmadaw(ミャンマー軍)の指令と統率の下で約28年間、政権の座に着いていたのであった(1958-60, 1962-1988)。彼らはさらなる23年間(1988-2011)を、命令による統治に甘んじる事となった。その影響力は今なお、実質的に偏在している。ビルマ/ミャンマーは近代史上、軍事的支配が最長でなくとも、最も長かった国の一つである。
I 近代ミャンマーにおける軍部の役割
ビルマ/ミャンマーは1962年以降、直接及び間接的な軍事支配の下にあった。その当時から、軍部は明らかに権力を永続的に掌握しようと画策していた。ミャンマー軍はそれ以来35年間、政令による直接統治を行い(1962-1974, 1988-2011)、さらには軍部の指示、統率下にあるBSPPのもとで間接統治を14年間行った(1974-1988) 。軍部の影響力は深く、あらゆる社会区分にまで及んでいる。彼らは全ての社会的移動性の道筋を支配してきた。軍部による経済の実効支配は、はじめはBSPPのもとで、後にはその公共部門への権限、さらには軍部によって組織、運営されるミャンマー経済持ち株会社やミャンマー経済株式会社、あるいは防衛省調達室の下にある諸企業を通じて行われてきた。あらゆるマスコミや輸入書籍、輸入資材に課された検閲は、成功には満たぬとしても、国民を政治的に近代化させ得る外的影響から隔離するための包括的な試みであった。
ミャンマー軍は比較的効果的のあった市民のための教育制度や医療制度を実質的に破壊する一方で、軍人やその親族達の暮らし向きが、策定者たちのために特別に計らわれた制度によって、はるかに良きものとなるよう、確実を期したのである。軍部は1980年に僧侶の登録という、あらゆる政権の長年の目標であった事をこなし、1982年には市民権を自分達に望ましい形となるように定義した。ガラスの天井が築かれ、これが非仏教徒(クリスチャンやムスリムたち)を実権から退けた。反乱を起こしていた少数民族集団と停戦を結ぶことにはなったが、概して少数民族の地域は軍の占拠する敵対的な領地、あるいは敵地として扱われていた。ミャンマー社会では、権力が機関よりも個人に集中するため、ミャンマー軍の上層部は個人的なつながりを通じて社会全体の支配を達成する事が出来たのである。
II 規律にあふれた民主主義: ミャンマー軍の将来的な役割を考える
2003年には、首相で軍事情報局長でもあったキン・ニュン大将が「規律にあふれた民主主義」のための7段階のロードマップを公表し、国家元首として、タン・シュエ大将がこれを規定した。この「規律」は事実上、軍部によって用意される事となったが、これは彼らの主要な目標である挙国一致、国家主権、軍事的自治権、さらには軍事予算や(そしておそらくは)彼らの代行人が得る事になる経済利益に対する支配権を持続させるためのものであった。
1993年以降にも、政府が出資し、大いにその筋書を行った新憲法のガイドライン策定のための全国会議が開催された時に、ミャンマー軍を政治分野の中心的機関に据える事が決定された。この事は憲法に規定され、次のように述べられている。(第6条)「ミャンマー連邦の一貫した目標は…(f)「国軍が国家の政治の指導的役割に参画する事を可能とする事」。(第20条も同様)。これは2008年のスターリン主義的な選挙によって承認されたものであった (これを早めたのは、おそらく2007年の僧侶による反政府デモ、「サフラン革命」によって生じたトラウマであろう)。軍部は重要な政治的地位を占める事となった。国や地方など、全ての議会の25パーセントが現役軍人で構成される事になり、彼ら自身は国防大臣から指名されるが、この国防大臣もまた、現役将校でなければならず、さらには(警察を取り仕切る)内務大臣や少数民族の地域を担当する大臣もまた同様とされた。国軍司令官は非常事態の際には政権を担う事ができる。大統領候補や副大統領候補(彼らは全員、間接的に議会から選出される)の近親者達は誰ひとり、外国勢力への忠誠を尽くす事はできない。ミャンマー連邦共和国からの離脱があってはならないのだ。憲法改正には議会の75パーセントの賛成が必要なため、軍部は提案された改正案を全て直接コントロールする事ができるが、彼らの支配下にあり、国会で大多数を占める連邦団結発展党(USDP)を通じても同様の事が行える事は言うまでもない。まるで単一体であるかのように振る舞うミャンマー軍は、理論上は軍部の支配を存続させるような制度を編み出した。この計画は理論的には完全で、軍部の支配を当面の間は保証するかと思われる。しかし、軍部が単一体のように見えたとしても、また、文法的には単一体であったとしても、経験は、これが首尾一貫した統一体であり続ける可能性が低い事を示す。個人的対立による影響が生じるだろう。側近たちやパトロン‐クライアントの関係が形成され、この単一性を厳しく試す事になるだろう。また組織的にも、BSPPの時代がそうであったように、現役将校と退役将校は、彼らの要求や目的でさえもが対立する事に気が付くかもしれない。米国議会調査局は新政府を「準民主」と表現するが、これはその上層部が退役軍人であるからだ。
III ビルマからミャンマーへ:社会的移動性の対比
新政府が発足した2011年3月のミャンマーは、軍事クーデター前夜の1962年3月1日のビルマとは社会的に極めて異なるものであった。当時、この国の少数民族(人口の1/3にあたる)の諸地域を除いたビルマ族の地域は、おそらく東アジア社会の中で最も移動性の開かれた地域であった。政権は多様で、内閣でさえもが民族的に開放されていた。移動性は原則として4つの道筋に存在した。教育制度は広く普及し、最貧層の男女でさえ、ラングーンやマンダレーの無料の大学に通う事ができたのである。サンガ(仏教の僧職)は開かれ、男性はその教育制度や大学を通じて身を立て、偉大な名声を残す事ができた。民間の政治組織やNGOは権力に通じる道であった。全ビルマ農民協会、全ビルマ労働者協会、退役軍人、その他の集団が、権力や権威を得るための手段であった。軍人自体は名誉ある職業であったし、勤め口よりも志願者の数がはるかに上回っていた。しかし民間部門では、基本的に外国人が優位であった。女性たちは社会、特に教育や医療関係の職業に目立っていたし、彼女たちはその他の多くの社会には無い法的権利を手にしていた。
50年に及ぶ軍事支配の後の現在との対比は、これ以上ない程までに鮮烈である。あらゆる移動性の道筋が軍部の支配下に置かれてきた。ミャンマー軍が大学に行く人間を決め、サンガは登録され、その教育機関は知的、及び運営上の支配対象となった。民間組織や民間部門はBSPPによって禁じられる、あるいは国家支配の要素となるかのいずれかとなった。ムスリムやクリスチャンが官職及び軍隊の管理職に就く事を認められず、大多数の少数民族もまた同様である中、軍は唯一の権力への道となった。どちらも軍事政権である(1988-2011)国家法秩序回復評議会(SLORC)と後の国家平和発展評議会(SPDC)が、(おそらくは1987年の中国を模範とする)「市民社会」の発展を許可したにせよ、これらの諸集団は事実上、代替的な政治方針に関与する事も、これを支持する事も阻まれていたのである。
東アジアで最も開かれた社会から、ビルマ/ミャンマーは意図的な軍隊式の支配を通じ、ミャンマー軍とその諸機関を「国家内国家」、あるいは国家そのものとさえするような社会になってしまった。最高の教育は軍事組織内にあり、これに反対する者や移動が可能であった者達は、国を離れ、雇用や政治上の憩いを求めて各地へと去って行った。推定では、50万人の教育を受けた人材が去ったとされる。さらにおそらくは、200万人の労働者達がタイへ避難、あるいは単純労働を求める事で、戦争や極度の貧困を逃れたのである。
IV ミャンマーの社会的コンテキストにおける国軍の将来
2011年3月30日の新政府発足にあたり、テイン・セイン大統領は、東南アジアで最も裕福な国であるはずのミャンマーを襲った大きな不幸を公式に認めた。彼は国家を変え、実際に社会の背後に存在するあらゆる局面の改革を試みている。それは容易な事ではない。力が不足している。たとえ改革に貢献するため、亡命中のビルマ人たちが呼び戻されたとしても十分ではない。変革のための正当で自由な発言は、様々な議会や、今、新たに規制の取れたマスコミにも存在する。軍事支配を弱める事に対する外部からの要求は、しばしば単純な言葉で述べられる。それはすなわち、憲法改正によって現役軍人を排除し、大統領を間接選挙で選出する規則を変えよというものである。
軍部のより穏健な役割に関する問題は、そう簡単に解決され得るものではない。なぜなら、多くの人が不適切と感じている憲法条項が軍事的支配の原因なのではなく、それはむしろ、より基本的な問題を反映したものであり、もっと長期的に取り組む以外の方法がないからである。軍部のより穏健な役割に関しては、即席の解決策が存在しない。憲法改正は、もっと基本的な問題を改善するためのアプローチなのである。
多元的な社会秩序の再構築には時間がかかるだろう。それは移動性の道筋を開く事で、国家の性質を変え、さらには軍部が自ら抱く優越感を変える事をも意味している。
実質的には退役軍人によって構成された与党が優位であっても、今や政治は開かれている。市民社会はより自由で、大学は検閲を廃止し、たとえ暗記学習が未だに主流であっても、知的硬直は廃されたのだ。学究生活がよみがえったのである。軍人は今でも望ましい職業であり、これが変わる事はないだろうし、その栄光も挽回されるであろう。軍と民のより近い関係は、互いへの敬意を若干回復する結果になるかもしれない。ミャンマー国軍が民間の政治家達を卑しく、腐敗した、役立たずだと罵ってきたこの数年間には、このような敬意が失われていた。進歩はおそらく今後10年にまたがるであろう。
しかし、問題は残されている。民間部門には公式の金融制度を通じた公的資本が欠けており、中国に独占される結果に終わるかもしれない。中国には事業拡大のために必要な資金を得る別の手段が存在する。この問題に取り組まなくてはならない。なぜならば、もし経済成長が行き詰れば、裕福な少数民族が(再び)国民の不満のスケープゴートとなる可能性があるからだ。
いくつかの比較例がミャンマーに起こり得る変化の道筋を明らかにするだろう。韓国は固定的な階級社会で、1961年から1987年までは軍部に支配されていたが、この国では軍部の権力からの撤退が平和裏に行われ、不平一つ出ないという事態が観察された。これは多様な社会的移動性の道筋が開かれたためであった。タイでは社会にそれ程強い軍事的支配が見られなかったが、これはタイ軍が権力への道を地方での政治や事業に見出してきたためである。インドネシアも、同様の穏やかなプロセスを始動している。これらの各社会では、名声や権力、権威への入り口が、以前は基本的に軍部によって独占されていたが、これが変化して成功への多元的な道筋となったのである。時が経てば、これがミャンマーにも起こるであろう。
皮肉なことに、また、直観に反して、我々はミャンマーがタイよりもはるかに容易く進歩する事を期待してもよいだろう。タイは極めて階級的な社会であり、発達はしているが、成長は停滞気味である。だが、ミャンマーでは、軍人は一般人と同じ出自から出世した者であり、たとえ軍のエリートの息子たち(中国では「幼君」)が陸軍士官学校で一目置かれていようとも、これもまた変わって行く事だろう。つまり、ミャンマーにはタイよりも平等主義的なビルマの権力体系へ移行するための、より大きな機会が存在するのだ。
ミャンマー軍は自分達の権力と権威を持続させるためのシステムを作ってきたが、これは徐々に失われて行く事だろう。これによって大多数のビルマ人たちにはより多くの機会が開かれ、そこには女性のための機会も含まれている。しかし、(民族、宗教の両方の)少数派には多元的な共存がもたらされるべきである。これは発現段階にあるようだが、その実現には、我々がまだ見ぬ政府の意図的な努力が必要となるだろう。
David I. Steinberg
翻訳 吉田千春
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 14 (September 2013). Myanmar
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 14 (September 2013). Myanmar